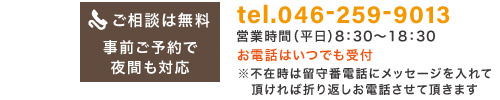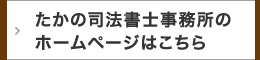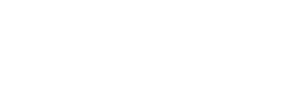Author Archive
遺言書ってどんなもの?終活に必要な遺言書の3種類の形式について
人生は終わりがあるものです。「自分の死を悲しんでくれる人に迷惑をかけたくない。」近年そう感じる方が増えているのででしょうか、就活ならぬ「終活」という言葉がテレビでもよく取り上げられています。「健康なうちにいずれ来る人生の終わりに対して準備をしておきたい」、「相続の際に家族にトラブルが起きてほしくない」など様々な思いで「終活」をする方がいらっしゃると思います。そこで必要になるのが遺言書です。自分の遺産相続を円滑に行ってもらうために欠かせないのが遺言書で、「終活の一環でとりあえず書いてみようかな」とお考えの方はたくさんいらっしゃいます。そこで今回はそんな遺言書の3種類の形式について簡単にご説明します。
・遺言書には3種類ある
一口に遺言書と言っても、大きく3種類に分けることができます。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言 の3つです。遺言者はこの3つのどれかを選んで、相続人に遺言を残すこととなります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者が自分一人で書く遺言書を指します。紙と、ペンそして印鑑があればいつでも作成可能で、法律の専門家に依頼する必要もないので費用も掛かりません。ただ、全文を自筆で書かないといけないため、身体的に書くことが難しい場合には他の種類の遺言によらざるを得ない事になります。また、一番手軽な自筆証書遺言ですが、素人だけで書いてしまうと内容の不備などが起きる可能性がどうしてもあります。不備がある遺言書は、その部分が無効、あるいは全体が無効になってしまします。なお、自筆証書遺言を手続きで使うためには、遺言者本人が死亡後に、後述の家庭裁判所での検認手続きを経なければなりません。
・公正証書遺言
確実に遺言書を残すために利用されるのがこの公正証書遺言です。遺言の内容を公証人に伝え、公証人に作成してもらいます。このメリットは、公証人が法的ルールに則って作成するため後に無効とされる様な危険がまず無い点、仮に遺言書を失くしてしまっても原本が公証役場に保管されている点です。また、家庭裁判所の検認手続きは必要なく、すぐに相続手続きに使うことができます。
この公正証書遺言を作成するには、証人が2人必要で、公証人への手数料等がかかります。
・秘密遺言書
遺言内容を他人に知らせたくない。こんな思いを遺言者が抱えることもあるでしょう。このようなときに利用されるのが秘密証書遺言です。自分で作って封印した遺言書を、公証人と証人2人の面前でさらに公証役場で封印します。内容を公証人がチェックすることは無いため、自筆証書遺言と同様に不備による無効の危険があります。内容を身内に知られたくない場合であれば、証人を全くの第三者にして公正証書遺言にする方が安全かと思います。
・遺言書の検認
公正証書遺言書以外の遺言書は本人の死後、家庭裁判所で相続人とともに開封され、存在を公的に認められる必要があります。この手続きを検認と言います。相続の各種手続きでは、検認手続きを経た遺言書が必要になります。また、封印された自筆証書遺言書を検認手続きを行う前に開封すると過料を科されてしまいます。
今回は遺言書の種類について簡単にまとめました。ぜひご参考にしてください。次回は遺言書の書き方についてご説明します。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
有効な遺言と無効な遺言
「こんな遺言書絶対認めない!」
このようなセリフを、ドラマの中で一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
これはテレビの中の話だけではありません。身内が亡くなった後に遺言書が見つかったけれど「書かれていることを本当に実行していいのか。」「不公平な内容で身内と揉めそう。」と悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。
そこで今回は遺言書の有効・無効についてご紹介します。
■遺言で書かれていて有効なもの。
遺言に書いて法的効力をもつ事項は民法等で決められています。それは大きく分けて3つあり、「財産」「身分」「執行」です。
まずは財産ですが、遺言書があれば法律に従った割合で相続することはなく、亡くなった人の意志に沿った財産の分配が可能になります。ただし、後に述べる遺留分に注意が必要です。
なお相続人以外の人でも受け取り可能で、遺贈といいます。
次に「身分」に関してですが、遺言で婚外子の認知を行うなどができます。
最後に「執行」ですが、きちんと遺言書の内容を執行してもらう人が選ばれていないと、遺言書通りに財産が分配されないかもしれません。また、相続人以外への遺贈の場合は執行者を選んでいないと面倒な手続きが必要になってしまいます。
■遺言書で無効になるもの
上記の内容以外の事が書かれた遺言は、例えば「家族みな仲良く暮らすこと」という記載は法的な効力は持ちませんが、遺言自体がそれで無効になるということはありません。他の記載事項は有効です。
無効に近い事項として、よく当事者で揉める原因の一つになるが「遺留分」です。
この「遺留分」に関しては、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害された相続人は、侵害された分をよこせと請求することができます(遺留分減殺請求といいます)。
次に無効になる(自筆証書)遺言の形式です。遺言が執行される時にはすでに遺言した本人は他界していて、本当に本人の意思で書かれたのか確認できないため、民法で決まっている形式で書かれているという事が一番重要視されます。
動画や音声で残された遺言や、パソコンで作成した遺言は無効になってしまいます。
また、うっかり抜けているかもしれない「日付」もなくてはダメです。
また、亡くなった本人のみが全文・日付・氏名を書いた遺言書でなければいけません。
■遺言書についてよくある疑問
まず、苗字が変わっている場合でも、旧姓で書いたものを書き直す必要はありません。戸籍を見れば分かるからです。
また、亡くなった方が悩んで何度も書き直したものが何枚も見つかる場合があります。その場合、日付の新しいものが有効になります。
そして亡くなった方の意思で書かれたものでなく、強要されて書かれたものは無効です。
最後に遺言書を見せる人を特定することはできません。
遺言書が有効・無効についてざっくりですがお分かりいただけたでしょうか。本サイトの遺言についての各ページに、より詳しく記載していますので、ご覧いただければと思います。
遺言書の言葉一つ一つに亡くなった方の思いが託されています。揉め事を少しでも起こさないためにもぜひ、遺産相続の際は参考にしてみてください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
死亡後にまずやらないといけない役所関係の手続き
大事なご家族が亡くなるとそのショックはとても大きいです。しかし、ご家族が亡くなった後に残された方がやらなければいけないことは沢山あります。その時になって何をしていいのかわからない、ということがないように今から相続手続きのやり方を少しでも知っておきましょう。
■死亡届の提出
死亡診断書が病院から発行されます。これは後々の手続きで必要な書類で、入手したらコピーをとっておきましょう。この書類はその方が亡くなったことを医学的かつ法律的に証明するものなので、これがないと死亡の証明ができず、火葬や埋葬、公共料金の支払い、年金受給、税金関係で混乱が生じてしまうこともあります。病院によって金額は異なりますが、大体5000円ほどかかります。入手したら印鑑と共に、死亡した地域か本籍地の市区町村役場まで提出しに行きましょう。
■年金受給停止の手続き
亡くなられた方が年金を受給していらっしゃった場合は、決められた日数以内に年金証書、死亡診断書、戸籍謄本などを用意して年金受給停止の手続きを行わなければいけません。受給停止の申請期間は、厚生年金の場合は死後10日以内、国民年金の場合は死後14日以内となっています。また、年金の給付は二か月ごとなので、一部未払いの場合もあります。その際は、その分の給付の申請を行ってください。
■介護保険の資格喪失届
亡くなられた方が介護保険の被保険者であった場合は、その資格喪失届けを市区町村に提出する必要があります。もし要介護認定を受けていたのなら、14日以内に介護被保険者証も返還しましょう。亡くなられた方が65歳以上かつ未納保険料がある場合は、相続人に請求されます。逆に保険料を納めすぎの場合には相続人に還付されるということも、合わせて覚えておきましょう。
■住民票の抹消届
これは死亡届の提出によって自動的に処理されるので、特別な手続きは必要ありません。しかし、亡くなられた方が世帯主であった場合には、世帯主変更届の提出が必要です。また、住民票の除票(住民登録が抹消された住民票)は、その後の手続きで必要になってくるので故人の住民基本台帳カードと届出人の身分証明書を用意して、取得しておくようにしてください。
■世帯主の変更届
亡くなられた方が世帯主であった場合、死後14日以内にこの手続きを行う必要があります。しかし、残された世帯員が一人、もしくは残された世帯員が15歳未満の子供とその親権者の2人である場合には必要ありません。
まずは上記の手続きを経たうえで、財産の相続手続きなどへ入っていくことになります。相続の手続きへ入る頃にはある程度落ち着いていると思いますが、上記はまだ混乱の最中で行わなければならないため、今のうちにおおまかな流れを掴んで頂ければと思います。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続放棄をするときの注意点
「亡くなった親父の借金が発覚した...」銀行系カード等がスピード審査で作れるなど、お金を借りやすくなった時代。
親が亡くなった後の相続放棄の可能性も他人ごとではなくなってきました。
「もし親に多額の借金があったらどうしよう。」と不安な方、またはすでに、相続放棄を申請しようと考えている方も中にはおられるでしょう。
そこで、今回は相続放棄を行うときの注意点とやるべきことをご紹介します。
■相続放棄をしようと決断する前に。
相続放棄を行うと、借金だけでなく、自分にとってプラスになること、つまり、継ぎたい遺産も放棄しなければいけません。
基本的に全てを引き継ぐか全てを放棄するかのいずれかの選択になります。ここが安易に相続放棄をしてはいけないといわれている所以です。
受け継ぐものの中に株や自宅が含まれている場合など、きちんとプラスとマイナスを考慮して、相続放棄の手続きを始めなければいけません。
また、相続放棄の申請期間は被相続人が亡くなった次の日から原則3か月以内となっています。
この期間内に家庭裁判所に申出書を提出しなければなりません。
■相続放棄を行うともう後戻りできない。
借金や遺産相続の争い、相続の際に必要な様々な手続きに関与しなくてよくなるところが相続放棄のいいところですが、デメリットも大きいです。
それは後から相続放棄の取り消しができないということです。詐欺や脅迫などの事情が無い限り取り消しはできません。
後から自分にとって大きな利益となる遺産が発覚しても相続することができないので、慎重に決断しなければなりません。
■相続放棄の前に相続財産に何があるのかきちんと確認。
相続放棄をするべきかどうか決めるには、自分が相続するかもしれない財産には何があるのかしっかりと把握する必要があります。
確認する内容は、預金はいくらか、不動産の有無、証券の有無、借金があるかどうかなどです。
これらの確認のため遺品の整理はある程度徹底した方がよいでしょう。タンスの引き出しの隅に知らなかった銀行通帳があるかもしれません。
現物がなくても郵便物や電話帳、日記などの記録から、何らかの取引が分かる場合もありますので、隈なく目を通すようにしてください。
今回は相続放棄を行う際の注意点とやるべきことを理解いただけたでしょうか。
手続きの詳細については、本サイトの相続放棄の各ページでより詳細に記載していますので、参考にして下さい。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言で揉めないために押さえておきたい5つのポイント
遺産相続で揉めないために遺言書を残そうかとお考えの方もいらっしゃるかと思います。しかし、その遺言書、ただ書けばいいというわけではないのです。今回は、そんな遺言書(自筆証書遺言)を書くときに気を付けたい5つのポイントについてお話しいたします。
■曖昧な表現は避ける
遺言書に記載されている表現が曖昧なために、実際にトラブルに発展してしまうこともあります。特に日付はきちんと明確に記載するようにしないと遺言書自体が無効になってしまうので、注意してください。具体的には「平成○○年○月吉日」が無効とされた裁判例があり、「平成○○年○月○日」と記載するようにしてください。 そして内容自体も、誰に、何を、どれだけ相続させるのか、明確に分かる表現を心掛けてください。特に「何を」では、不動産は登記簿を見ながら、預金は通帳を見ながら、株式や証券は証券会社の資料を見ながら記載することをお勧めします。例えば、「海老名の家は長男に」と記載している場合、海老名市内に自宅のほか貸家も持っていると、自宅のみか両方なのか分からず手続きができないといったことも起こりえます。
■相続財産の場所も記載しておく
現金や預金、不動産、株式や有価証券のほか、宝石類、美術品、骨董品なども相続財産になります。これらの財産分与の仕方について記載しても、その所在が分からないと分けられません。自宅内に全部保管してあれば良いのですが、身内の誰かや、信頼できる第三者に預けているなど、財産の所在を被相続人のみが知っている場合、忘れずにその保管場所も記載しておきましょう。「財産目録」という財産一覧表のようなものを別に作成しておくのもいいでしょう。
■遺言書の保管場所
遺言書は残された方たちにとって、非常に大きな意味のあるものです。したがって、一度作成したらそれが必要になるときまで、厳重に保管しておかなければなりません。特に自筆証書遺言はご自身で気軽に作成できる分、保管もご自身でしっかり行わなければいけません。ただ逆に、あまり厳重にしすぎると相続人の誰も見つけられず、みな遺言書は無いと思って手続きを進めてしまう事もありえます。後記の遺言執行者や、信頼できる者に託しておくか、自分の金庫などに保管する場合は亡き後に所在が分かる様にほのめかしておくなどが必要です。 なお、銀行の貸金庫は注意が必要です。遺言書で遺言執行者を定めていれば、遺言執行者が貸金庫を開けることができますが、そのためには遺言書を提示することが必要です。ところが、その遺言書が貸金庫の中にあるとそもそも開けなければ提示できません。その場合は、相続人全員の同意書で開けることになりますが、協力しない相続人や連絡のつかない相続人がいると貸金庫を開けることができず、せっかく書いた遺言書を取り出すことができなくなります。
■遺言執行者を決めておく
遺言内容をそのとおりに実行するのが「遺言執行者」です。相続人の中の1人を遺言執行者にすることが多いのですが、遺言書の内容で相続人間で揉める可能性がある場合には、この役割を家族以外の信頼できる方に頼んで、遺言書に明確に記載しておく方が良いかと思います。遺言書を作成するときに協力してもらった弁護士、司法書士、行政書士などに遺言執行者を依頼する方も多くいらっしゃいます。
■遺言書の内容変更は遺言書で行う
遺言書の内容を後日変えたいという場合もあるかと思います。そんな時は必ず遺言の方式で行わなければなりません。内容すべてを撤回したいのであれば、遺言書自体を破棄すればそれで大丈夫です。一部を変更したい場合は、変更したい内容だけ別で新しく遺言書を作成します。訂正印を押して書き直すのではないことに注意してください。
以上のポイントに気を付けて遺言書を作成してください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
法務局による法定相続情報証明制度
6月から、法務局による法定相続情報証明制度が開始されました。
相続登記のほか、銀行や証券会社での相続手続きには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍が必要になります。だいたい5通以上、多い方だと10通以上になる方もいらっしゃいます。
通常は各1通取得して、各種手続きに原本を提出してコピーをとってもらい、原本は返してもらって次の手続きで使う、を繰り返します。郵送でやり取りする場合には、原本が返ってくるまで次の手続きができない事になります。
法定相続情報証明制度は、法務局に、相続関係が記載された図と一緒に除籍等を提出すると、その図に記載された相続関係で間違えないという証明をしてくれるものです。相続関係図を必要な手続きの数だけ発行してもい、その証明図を提出すれば、原本を返してもらってという手間が省け、また各種手続きを一度に平行してできます。
法務局への申請は、相続人本人で行うか、司法書士などの一定の資格者に代理で行ってもらう事になります。
手続きの詳細については、いつでもお問い合わせ下さい。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続遺言など無料相談会(海老名・座間)
今月と来月も、海老名市、座間市で2回、行政書士さんと一緒に無料相談会を開催します!!
なお、海老名ではいつも文化会館で行っていたのですが、今月から、海老名郵便局で行う事になりました!!
入口を入ってすぐのスペースで行いますが、状況に応じて、行政書士さんの事務所がすぐ向かいにあるため、そこで相談をお受けする事もできます。
5月23日(火) 9:30~18:00 海老名郵便局
6月16日(金) 9:30~18:00 海老名郵便局
6月17日(土) 10:00~16:30 サニープレイス座間
予約無しでも大丈夫ですが、混みあっているとお待ち頂くこともあるため、事前にご予約いただいた方が良いかと思います。
ご予約電話は、たかの司法書士事務所 046-259-9013 まで。
サニープレイス座間の場所については、 こちら をご覧ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続遺言など無料相談会開催(海老名・座間)
今月は、海老名市、座間市の2か所で行政書士さんと一緒に無料相談会を開催することになりました!!
3月18日(土) 10:00~16:30 サニープレイス座間にて
3月20日(祝) 10:00~16:30 海老名市文化会館にて
予約無しでも大丈夫ですが、混みあっているとお待ち頂くこともあるため、事前にご予約いただいた方が良いと思います。
ご予約電話は、たかの司法書士事務所 046-259-9013 まで。
サニープレイス座間の場所については、 こちら をご覧ください。
海老名市文化会館の場所については、 こちら をご覧ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続遺言など無料相談会開催(海老名・綾瀬・座間)
今月は、海老名市、綾瀬市、座間市で計3回、行政書士さんと一緒に無料相談会を開催することになりました!!
2月18日(土) 9:00~12:30 綾瀬市中央公民館にて
2月19日(日) 10:00~16:30 サニープレイス座間にて
2月28日(火) 10:00~16:30 海老名市文化会館にて
予約無しでも大丈夫ですが、混みあっているとお待ち頂くこともあるため、事前にご予約いただいた方が良いと思います。
ご予約電話は、たかの司法書士事務所 046-259-9013 まで。
綾瀬市中央公民館の場所については、 こちら をご覧ください。
サニープレイス座間の場所については、 こちら をご覧ください。
海老名市文化会館の場所については、 こちら をご覧ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続・遺言など無料相談会開催(海老名・綾瀬・座間)
今月は、海老名市、綾瀬市、座間市で計3回、行政書士さんと一緒に無料相談会を開催することになりました!!
1月21日(土) 9:00~12:30 綾瀬市中央公民館にて
1月22日(日) 10:00~16:30 サニープレイス座間にて
1月31日(火) 10:00~16:30 海老名市文化会館にて
予約無しでも大丈夫ですが、混みあっているとお待ち頂くこともあるため、事前にご予約いただいた方が良いと思います。
ご予約電話は、たかの司法書士事務所 046-259-9013 まで。
綾瀬市中央公民館の場所については、 こちら をご覧ください。
サニープレイス座間の場所については、 こちら をご覧ください。
海老名市文化会館の場所については、 こちら をご覧ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。