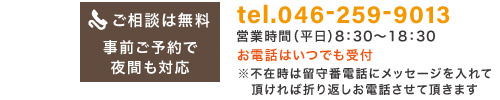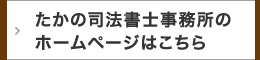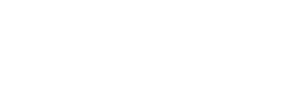Author Archive
遺言書の検認手続き「封印付き遺言書は開封してはいけない!」
封印された遺言書はすぐに開封してはいけないということをご存知でしょうか。
開封しない状態で、家庭裁判所による「検認」の手続きをする必要があります。
大切な方の遺言書、だからこそ早く開けて内容を確認したい気持ちになると思いますが、封印された遺言書は、「検認」の日まで内容の確認はできません。
今回は遺言書の検認についてご説明します。
■遺言書の種類
遺言書は、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類に分類されます。
・自筆証書遺言とは
この遺言書は、遺言者が自身で作成し自宅で保管します。
そのため自筆証書遺言と呼ばれます。
・秘密証書遺言
この遺言書は、遺言者が自身で作成し、保管だけ、公証人役場に頼みます。
・公正証書遺言
この遺言書は、公証人役場の公証人が遺言者と相談しながら作成し保管します。
■封印のある遺言書は開けてはいけない
自宅から遺言書が見つかった。もし遺言書に封印があれば、勝手に開けて見てはいけません。
家庭裁判所で検認手続きを行い、その際に開封します。
なお封印とは、封筒の封を閉じて印鑑を押したものを言います。封を閉じていても印鑑を押していないものは封印ではありませんので、開封しても問題はありません。
■遺言書の検認
封印の有無にかかわらず、自筆・秘密証書遺言は検認手続きが必要です。
家庭裁判所で相続人全員が集まり、確認することになります。
目的は2つあります。
・遺書の有無・内容を告知すること
・遺言書の偽造を防止すること
です。
まず、申立人(保管者・発見者)が検認申立を行います。
すると、裁判所から相続人全員に検認日時が通知されます。
当日、裁判所で検認します。
検認が済んだら、検認済証明書をもらいます。
その後、遺言書を使って各種の相続手続きを行います。
■申立人
通常、遺言書を発見した人もしくは遺言書を頼まれて持っていた人が、検認申立を行います。
■遺言書を検認前に開封した場合
5万以下の過料が課されてしまいます。
さらに遺言書に偽造変造の疑いがある場合は、過料だけでなく遺言書の効力自体も問題となってきます。
■まとめ
・自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所で「検認」が必要である。
・「検認」まで、封印付き遺言書を開封してはいけない。
・遺言書がある場合は、家庭裁判所に検認済証明書をもらってから、相続手続きが行える。
以上が遺言書の検認手続きの説明でした。
たかの司法書士事務所では、遺産相続に関する手続きをお手伝いしています。
ご連絡お待ちしております。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続放棄手続きの流れ、注意点まで詳しく解説
「親が亡くなってしまった。借金まで相続したくはない。」
家族が、財産や債務の相続権を放棄する方法である「相続放棄」をご存知でしょうか。
最も多いのは、遺産の中に借金が多く含まれているときに相続放棄をするケースです。
今回は相続放棄手続きの流れ・注意点について解説します。
1相続放棄とは
相続放棄とは、被相続者の法定相続人になった時、財産と負債を承継する地位の全てを放棄することで、相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとされます。
2相続後の流れ
相続が開始されると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
「単純承認」は、被相続人の土地の権利や財産、また、借金返済の義務を全て相続することです。
「限定承認」では、相続できる財産はあるが、負担する負債もありその額が明確でない時、相続した財産を限度額として被相続人の借金返済を行う意思を示します。
「相続放棄」は、前段落で説明しました。
3「相続放棄の申述」と「申述可能な期間」
「相続放棄」または「限定承認」を選択するなら、相続人は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」に申述書を提出する必要があります。
「相続放棄」の場合、「相続開始を知ったときから3カ月以内」に、家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出します。
後に家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が送られてきて、この文書の質問欄に回答して返送すると、「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。
4注意点
・相続開始を知った時から3カ月以内に申述しなかった場合は、単純承認したと判断されます。
・相続放棄しても「相続人が相続財産の一部または全部を隠した、自分のために消費した、財産目録に意図的に記載しなかった」場合、次順位の相続人が単純承認していない限り、単純承認したものと扱われます。
5まとめ
・相続人となったら、相続放棄・単純承認・限定承認のいずれかを選ぶ。
・相続放棄と限定承認には手続きが必要である。
・相続開始を知った時から3カ月以内が相続放棄申述期間である。
・相続放棄申述期間に申述しないと単純承認したとみなされる。
以上が、相続放棄手続きの流れと注意点でした。
たかの司法書士事務所では、相続放棄手続きをお手伝いしています。
不安な点や分からないことがありましたら気軽にご相談ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
司法書士などの専門家に遺言書を相談する意義
「遺言作成は、本当に司法書士などの専門家に相談・依頼する意味があるの?」
と思われる方も多いと思います。
今回は「専門家に遺言書を相談する意義」について解説します。
■遺言書の種類
遺言書には一般的に以下の2種類あります。
・被相続人が自分で遺言を書き、自分で保管する「自筆証書遺言」
・公証人に遺言書を作成してもらい、保管してもらう「公正証書遺言」
■遺言書について相談を行っている専門業者
司法書士、行政書士、弁護士、税理士、信託銀行など、遺言書に関わる業務を行っています。
■専門家は「実際の遺言書を書かない」
自筆証書遺言の場合、司法書士などの法律の専門家に依頼しても、法律の規定上、実際に紙に書くのは遺言者本人です。
公正証書遺言の場合、公証人が遺言書を作成します。
つまり、専門家は「遺言書を書いてくれる」わけではありません。
■専門家の業務内容
1.被相続人の望む相続結果になるような文案を構成してくれる
2.法的に有効な遺言書の作成方法を教えてくれる
3.遺言書を保管する
4.遺言書の存在を相続人に通達する
5.第三者としての遺言執行
6.「公正証書遺言」の場合、必要な証人2人になってくれる
7.公証人との打ち合わせを代行してくれる
■公証人の業務内容
公証人は、検事や裁判官、法務省の職員など法律関係の方が退官後に任命される方たちで、法律の知識が豊富で以下の業務を行っています。
1.法的に有効な遺言書の作成方法を教えてくれる
2.「公正証書遺言」の場合、遺言書を作成してくれる
3.遺言書の原本を保管する
■司法書士などの専門家に相談する意義
司法書士などの専門家に相談する一番の意義とは、やはり、「相続に関して被相続人の望む内容を提案してくれる」ことです。
他には、「自筆証書遺言の場合も遺言書を保管してくれる」「公証人との手続きを代行・手助けしてくれる」なども大きな意義です
以上が遺言書について司法書士などの専門家に相談する意義に関する解説でした。
たかの司法書士事務所では、遺言作成、遺言執行の業務も行っています。
ご連絡お待ちしております。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言書が見つからない場合の、自筆証書遺言を探す方法とは
「遺言書が見つからない。どう探せばいいのだろう。」
ご家族の葬儀の後、相続などの問題が発生します。
遺言書の存在を家族に伝えていない場合、ご家族は自身で遺言書を探す必要があります。
前回は「公正証書遺言」の探し方についてご説明しました。今回は、「自筆証書遺言」の場合の遺言書の探し方をご説明します。
■自筆証書遺言の探し方
1.自宅を探す
自筆証書遺言は、多くの場合自宅に保管されています。
被相続人の遺言書を探してみましょう。
2.銀行の貸金庫を調べる
被相続人が、自筆証書遺言を銀行の貸金庫に入れている場合があります。
被相続人の方がお亡くなりになった後、相続人全員の立会いのもと、貸金庫の中身を確認できます。
しかし、わざわざ遠方から相続人全員が集まったとしても、貸金庫内に遺言書がない場合もあります。
3.被相続人と関係のあった専門家や知人に尋ねる
被相続人が、「遺言書の作成・保管・執行」を「司法書士、行政書士、弁護士、税理士、コンサルタント、信託銀行」などの専門家に依頼していることがあります。
そのため、被相続人が保管していた名刺にこれらの専門家の名刺があれば、遺言書について何か知っている可能性があるので、連絡してみましょう。
これらの専門家は、遺言書保管料を一定期間ごとに頂いていることもあり、その場合は振込が止まると被相続人に連絡を取ったりします。
被相続人の家族と連絡がつくと、被相続人がお亡くなりになったことを知りますから、その後に「遺言書の開示・執行」を行ってくれます。
このように、専門家の方からの連絡で遺言書の発見に至ることもあります。
※自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になります。
また、封印付きの遺言書は「検認」まで開封してはいけません。
これは、遺言書の偽造や改ざんを防ぐ役割があります。
もし検認以前に開封してしまうと、過料が科せられます。
封印のある自筆証書遺言の場合、勝手に封印を開けないようにしましょう。
以上が「自筆証書遺言の探し方」についての説明でした。
たかの司法書士事務所では、遺産相続・遺言書に関する手続きをお手伝いしています。
ご連絡お待ちしております。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
公正証書遺言における遺言書を探しだす方法とは
「父は遺言書を作った様な事を言っていたが、見つからない。どう探せばいいのだろう。」
このように、遺言書の探し方がわからない方も多いのではないでしょうか。
亡くなられた方の意思を尊重するために、早々に諦めるのではなく、できる限りのことをするべきでしょう。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類あり、それぞれ探し方が異なるということを知っておくと見つかりやすいです。
今回は、「公正証書遺言」の場合の遺言書の探し方をご説明します。
■公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、数種類に分類される遺言書の中で、公証役場で公証人に作成してもらい、公証役場で保管するタイプの遺言書のことです。
自筆証書遺言は自筆で遺言書を書かなくてはいけませんが、公正証書遺言では「公証人」が遺言書を作成してくれます。
■公正証書遺言の探し方
公正証書遺言は、公証役場に保管されているので、お近くの公証役場を訪れ、検索システムを使うことで、公正証書遺言がどこに保管されているか分かります。
そのため、自筆証書遺言の場合のように、被相続人の自宅や知人、専門家、銀行の貸金庫などを周る必要がありません。
多くの場合、「被相続人が遺言書を用意していたかどうか」「用意していたならば、公正証書遺言なのか、自筆証書遺言なのか」分からないと思いますので、まず、公証役場で公正証書遺言を検索するのが良いでしょう。
また、遺言書を複数作成している場合もありますので、公正証書遺言が見つかっても自筆証書遺言も探してみる必要があります。
■探す際に必要な資料
以下に、公証役場で検索してもらう際に必要になる資料一覧です。
1.亡くなったことが記載されている被相続人の戸籍謄本
2.検索依頼者が相続人であることを証明できる戸籍謄本
3.検索依頼者の3カ月以内の印鑑証明書と実印、または、写真付き身分証明書と認印
■まとめ
・公正証書遺言は公証役場の検索システムで探せる。
・公正証書遺言が見つかっても、自筆証書遺言も探す必要がある。
・公正証書遺言の検索には、上記の1~3の資料が必要になる。
以上が「公正証書遺言の探し方」についての説明でした。
たかの司法書士事務所では、遺産相続・遺言書に関する手続きをお手伝いしています。
ご連絡お待ちしております。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
「遺言書の撤回」に関する3つのケースと5つの方法
「遺言書の内容をどうしても変えたい」
「どうしたらいいのか」
遺言書は、一度書いても後で修正したいというケースは多いようですので、このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
今回は「遺言書の撤回」に関する3つのケースと5つの方法に分けてご説明します。
■遺言書の撤回
被相続人は生きている間に既に作成した遺言書を撤回できることが民法1022条に明記されています。
■遺言書の撤回方法
1.遺言書を一つも残さない場合
・遺言書を破棄する
「自筆証書遺言」で、自身で遺言書を保管している場合は、破棄することですでに作成した遺言書を無効にできます。
作成した遺言書が「公正証書遺言」の場合、原本が公証人役場にありますので、手元の「正本」「謄本」を破棄しても遺言の撤回にはなりませんので、ご注意ください。
2.新しく遺言書を作らない場合
・遺言書を訂正する
「自筆証書遺言」であれば、自身で遺言書を保管しているので、訂正することで内容を変更できます。ただし、訂正方法は厳格に定められていますので、注意が必要です。
・生前処分など遺言後の法律行為に抵触する行為をする
遺言書に「Aに自宅を遺贈する」と記載していても、生前にBに譲渡していれば、その部分だけは遺言の法的効力がなくなります。
この場合、遺言書を書き直したり新しく遺言書を作成する必要はありません。
3.新しく遺言を作る場合
・条項を入れた新しい遺言を作る
「被相続人は、○年△月×日に作成した遺言を全部撤回する」という条項を新しい遺言書に加えることで、前の遺言書の全ての内容を撤回できます。
・前の遺言の内容と抵触する新しい遺言を作る
「被相続人は、○年△月×日に作成した遺言を全部撤回する」という条項が新しい遺言書になくても、以前の遺言書と抵触する内容が新しい遺言書に書いてあれば、法律上、新しい遺言書の内容が優先されます。以前の遺言書の、新しい遺言書に「抵触する部分」だけが撤回されます。
■まとめ
・「遺言書を一つも残さない場合」「遺言書を新たに作らない場合」「遺言書を新しく作る場合」の3つのケースに分類できる。
・自筆証書遺言は、撤回したい遺言書を破棄または訂正することで撤回できる。
・生前処分など、遺言書の内容と抵触する行動を被相続人が生前に行っていた場合、遺言書の「抵触する部分」は撤回されたことになる。
・新しい遺言書を作って前の遺言書を撤回する場合2通りの方法がある。
以上が遺言書の撤回方法に関する解説でした。
たかの司法書士事務所では、遺言作成、遺言執行の業務を行っています。
不明な点や不安なことがあれば、気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
借金の相続を逃れる方法ー相続放棄とは
相続権の放棄をお考えの方の中には、
「親の遺産を相続しようとしたら、多額の借金があった…」
「債務超過で相続するメリットがない…」
このようなお悩みを抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
資産を超えるほどの債務を相続してしまう、一部の相続人に相続権を集中させたいといった理由で相続放棄を選ぶ方がいらっしゃいます。
そこで、ここでは、相続放棄によって何ができるのか、どのようにすれば相続放棄できるのかをご説明します。
■相続放棄にはどんな効果があるのか
「相続放棄」をすると、「初めから相続人とならなかった」ものとされます。相続人としての一切の権利義務がなくなります。
相続放棄を利用すれば、超過している債務から逃れたり、相続資産を一部の相続人に集約したりできます。
遺産の権利を集約することは遺産分割協議でも可能です。しかし、債務を免れるには、相続放棄によるしかありません。
債務を相続してしまった場合、相続人に返済の義務が発生します。放置していると、相続資産を差し押さえられるだけでなく、相続人自身の資産も返済資金の対象となる可能性があります。
ただし、相続放棄をすると資産に対する相続権も放棄することになるので、不動産や骨とう品など欲しい物だけをもらうということはできないことに注意してください。
■相続放棄をする方法とは
相続放棄をするには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続開始から3か月以内に、相続放棄申述書という書類を家庭裁判所に提出してください。
同時に、被相続人の戸籍の附票または住民票の除票、被相続人の死亡が分かる除籍、申述人の戸籍謄本、が必要です。
相続放棄には期限があります。
民法第915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄か限定承認か単純承認を選ばないといけないと規定しています。
通常は被相続人の死亡日から3カ月ですが、被相続人の死亡を知らなかった場合や、存在が認知されていない資産・負債があった場合には、相続の開始が被相続人の死亡日より後だとされる場合もあります。
また、相続人が複数いる場合に他の相続人から相続放棄することの承認・許可を得る必要はありません。
つまり、債務超過などで相続放棄をする必要があると判断すれば、相続人それぞれがご自身の判断でできます。
相続放棄の手続きはそれほど複雑ではありません。
ただし、相続放棄が必要かどうかを判断するには、資産と負債の多少を見極める必要がある場合もあります。その場合には、専門家に相続資産の状況を診てもらうの事をおすすめします。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続の面倒な手続きに失敗しないための方法
「親がなくなって相続が発生するけれど、なにか手続きをしなければならないのかな…」
専門家でなければ、ほとんどの方が相続手続きの経験はないでしょう。相続のための手続きはいくつかありますが、ほとんどの手続きはそれほど難しくなく、数も多くないため、ご自身でも十分こなせます。
しかし、不動産の登記のような不慣れな手続きや、ご逝去の後の気が動転しているときの手続の際には、なかなか冷静になれないものです。
そのため、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
ここでは、相談するにあたってまずは知っておくべき、遺産相続に必要な手順をご紹介します。
■遺産相続に関する手順
遺産相続をするときには、場合にもよりますが、以下の4つの手順が必要です。
・遺言書の確認
・相続人の確定
・相続財産の全容を把握
・相続税申告
まずは、「遺言書」があるかどうか、あればその内容を確認します。
相続分割の分配を決めるのに必要だからです。遺言書があり、その内容が法的に有効であれば、それに従って遺産の分配が決まります。
ただし、必ず遺言書に従わなければならないわけではなく、相続人全員が遺産分割協議を行うことで財産を分配することも可能です。そのときには「遺産分割協議書」の作成が必要です。
相続にあたっては、「相続財産の全容を把握する」必要があります。
遺族が知らない相続資産があったというケースはよくあります。
また、相続財産には、不動産や株のようなプラスの資産だけでなく、借金のようなマイナスのものも含まれています。
そのため、見逃しているものはないか、債務超過になっていないかなどを確認します。
仮に、債務超過になっている場合は、「相続放棄」によって負債を免れることもできます。
ただし、同時にその他の財産の所有権も失うので注意してください。
また、不動産を相続した場合には、「名義変更登記」をする必要があります。
遺産総額が、相続税の基礎控除額を上回る場合は「相続税の申告」をする必要があります。
基礎控除額を明らかに下回る場合は、申告の必要はありません。
申告が必要な場合、10ヶ月以内に相続税申告を行わなければ、無申告加算税という通常の税率よりも加算された税金を支払わなければなりません。また、基礎控除以外の、配偶者特例や小規模宅地特例を適用することもできなくなってしまいます。
遺産相続のためにはこのようないくつかの手順があります。
ご自身でできないわけではありませんが、手続きに期限があったり、素人では判断できないこと(例えば、財産と負債の見極め)があったりするので、専門家に相談することをおすすめします。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
気軽に相続の相談をできる無料相談所の利点とは
「親が亡くなったので遺産相続が発生するけど、どのように分割するのか分からない。」
「自分がなくなるときに子どもたちにより多く財産を残すにはどうすればいいんだろう。」
相続について、親や子など様々な立場で皆様お悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
専門家でなければ相続問題について慣れている方はほとんどいないので、ちょっとしたことでも分からないことがあります。
そのような時は誰かに相談したいものですが、いきなりお金を払って司法書士などの専門家に相談するというのはハードルが高いのではないでしょうか。
そこで利用できるのが無料相談です。
ここでは、どんなところに相談所があるのか、無料相談をする2つのメリットをご紹介します。
■無料相談所はどこにあるのか
相続相談を無料でできるところは全国にあります。
民間の司法書士事務所や弁護士事務所が独自に相談センターを運営している場合もあれば、地域に相続相談の社団法人が立ち上がっているところもあります。
また、各行政の役所で定期的に司法書士・税理士・弁護士・行政書士などの無料相談を設置している場合も多くあります。
神奈川県海老名市にある「たかの司法書士事務所」もそんな無料相談ができる場所の一つです。
司法書士事務所ですが、他の士業の方と協力して業務を行っているため、司法書士として悩みに答えるだけでなく、悩みを解決するのに適した士業が誰かを診断することもできます。
■無料相談の何がいいのか
無料とはいえ、相談時間がかかるのでなかなか行く気にならないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、無料相談に行くメリットを2つご紹介します。
◇メリット1:あなたの現状がわかる
無料相談なら、お金の心配をせず気軽に状況を把握できます。
相続が発生するといっても、財産の種類や相続人の数など状況によって必要な手続き・それをいつまでにしなければならないのかなど人によって状況が異なります。
ネットで情報を調べればある程度のことは分かりますが、正確にあなたの状況を知るためには専門家に相談するのが良いでしょう。
◇メリット2:ふさわしい相談相手が分かる
相談相手を選ぶことは重要です。
それは、抱えている問題によってどの士業者に相談するべきなのか変わるからという理由もあれば、同種の士業、例えば司法書士のなかで誰を選ぶかも重要になるからです。
無料相談を利用すれば、リフォームで見積もりを取るように個々の士業者の良し悪しも判断できます。
もちろん、実際に手続きを依頼することになれば費用が発生しますが、相談だけなら無料だという場合には、ぜひ活用してみてください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言書を適切に書くには専門家に相談しよう
「正しく遺言書が書けるか心配だから誰かに相談したい。でも誰に相談すればいいんだろう…」
このようなお悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
遺言書には、弁護士や司法書士などの多くの専門家が関わります。そのため、どの専門家を頼ればいいのか、またこれらの専門家に頼るメリットは何なのか、気になるかと思います。
そこで、ここでは専門家の中から司法書士を選ぶのが良い場合と、司法書士に遺言書の作成を相談・依頼する3つのメリットをご紹介します。
■遺言書作成をどの専門家に相談・依頼するか
遺言書の作成を手伝える士業には、司法書士、弁護士、税理士などがあります。それぞれの特徴を見ることが専門家選びの役に立ちます。
◇司法書士
司法書士は、相続財産に不動産が含まれている方に向いています。
司法書士は不動産や法人の登記手続きを担う専門家です。
そのため、一般的には不動産の相続に関する知識は豊富だと思われます。
◇弁護士
弁護士は、遺言内容が遺留分などで相続人間の紛争が予想されるものである方に向いています。
例えば、遺言によって遺産の全てを法定相続人でない者に相続させることができます。
しかし、法定相続人には遺留分減殺請求によって自分の相続権を主張できるので、結果遺言上の相続人と法定相続人の間で紛争が生じます。
このように、紛争を起こしそうな遺言内容については、法律の専門家である弁護士を頼るのが良いかもしれません。
◇税理士
税理士は、相続税が発生する恐れのある方に向いています。
相続時に相続税が発生する方はそれほど多くないかもしれませんが、基本控除額を越えそうな方は税理士に相談をするのが良いかもしれません。
■遺言書作成を専門家に相談・依頼する3つのメリット
◇メリット1:法的に有効な遺言書が書ける(自筆証書遺言)
ご自身で遺言書を書く場合に最も不安なのは、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうことではないでしょうか。
しかし、専門家に相談すれば、事務所によりサービス内容は異なりますが、法的に有効な遺言書を書く手伝いをしてもらえます。
◇メリット2:役場に行く手間が省ける(公正証書遺言)
公正証書遺言を書く場合、証明書類の収集や公証人との事前やりとりのために自治体の役所や公証役場に行く必要があります。
しかし、役所も公証役場は平日しか開いていなかったり、公証役場が自宅・職場から離れていたりと負担が多いこともあります。
専門家に作成を依頼すると、代行によってこれらの負担を軽減できるかもしれません。
◇メリット3:証人になってくれる(公正証書遺言)
公正証書遺言を書くには、2人の証人が必要です。家族や親戚の多くは、この証人にはなれません。
遺言作成はお金のことが絡むデリケートな話なので、友人に証人になってもらうのも憚れるでしょう。
そんなとき、専門家に公正証書遺言の作成を依頼するなかで、証人にもなってもらえます。
遺言書の作成は、ご自身でするには難しい点が多くあります。
公正証書遺言を作成するにしても、個人でやるには多くの負担があります。
司法書士など専門家に相談すれば、これらの問題を解決できるかもしれません。ぜひご相談ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。