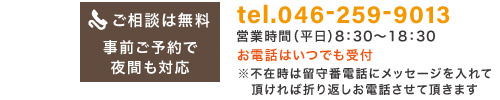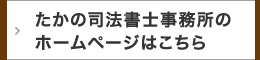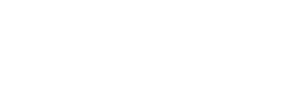Author Archive
預貯金の仮払いの創設|相続法改正案の内容とは?
■はじめに
相続に関する民法改正案の中で、預貯金について、遺産分割前の仮払いを可能にする制度の創設が提案されています。
■預貯金の仮払い制度の創設は何を意味する?
以前、裁判所は、預貯金については相続開始と同時に相続分に応じて分割され、それぞれの相続人が各自単独で相続分について金融機関に払戻請求でき、遺産分割の対象にならないとしていました。しかし、平成28年12月に最高裁が判例を変更して、預貯金も遺産分割の対象になるものしました。
そのため、相続開始後、遺産分割がなされるまでは、相続人の一人から払戻しを請求しても、金融機関はこれを拒むことができることが明確になりました。
そうすると、被相続人の預貯金を使わないと相続債務や葬儀等費用の支払いなどができない様な場合に、困った事になってしまいます。
そこで、民法改正案では、遺産分割前でも一定額であれば仮払いを認める制度の創設が提案されています。
■仮払いの2つの手続き
・金融機関の窓口で請求
相続人の一人が、金融機関の窓口へ行って仮払いの請求をする場合、各口座ごとの預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分、といった基準で上限額を定める提案がされています。
なお仮払いを受けた場合は、後日の遺産分割の際に具体的な相続額から差し引かれます。
・家庭裁判所の保全処分を利用する方法
家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをする際の、保全処分として、仮払いの申立てをする方法が考えられています。
手間とコストがかかり、家裁に認めてもらうために仮払いが必要であることの疎明も要しますが、家裁が認めてもらえる限りにおいて、上記のような上限額は特に設けられません。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
民法改正案による配偶者の住居相続への影響について
■はじめに
2018年の3月13日の国会にて、相続法の一部分が改正される法律案が提出されました。
今回はその中で、住居の相続に関わる点についての変更をご紹介します。
■配偶者の居住権の創設
・配偶者が継続して自宅に住むことができる「配偶者の居住権」
現行法では、故人と同居していた配偶者が自宅に継続して居住するのを確実にするためには、遺産分割などで所有権を取得するしかありません。遺産総額の中で不動産は大きな価値を占める事が多いため、遺産分割で自宅の相続を受ける代わりにその他の金融資産(預貯金など)はほとんど他の相続人に持って行かれるという結果になることも生じます。
それを踏まえ、民法改正案では、「配偶者の居住権」の創設が提案されています。この「配偶者の居住権」は、亡くなった被相続人が所有していた住居に配偶者が同居していた場合、無償で継続してその住居に住むことができる権利のことを指します。
・配偶者の短期居住権と長期居住権
この「配偶者の居住権」には、「短期の居住権」と「長期の居住権」が提案されています。
短期の居住権は、相続開始により当然に生じる権利で、遺産分割によりその住居を誰が相続するか確定する日、または相続開始から6カ月が経過する日のいずれか遅い日まで、の権利とされています。結果的に住居を立ち退く状況になるにしても、それまでの猶予期間を法的に与えるものです。
長期の居住権は、配偶者が原則として終身、その住居に住み続けることができる権利です。この権利は、遺言、死因贈与、遺産分割によって取得することができる権利です。法律上当然に与えられるものではありません。例えば遺産分割で、自宅不動産は長男が相続するが、妻が居住権を取得するという内容にすることができます。
この長期居住権は、所有権を相続するよりも評価額としては低くなる(評価方法については検討中のようです)ため、その分、他の金融資産(預貯金など)を多く配偶者が取得することが可能になります。
■20年贈与を受けた配偶者の保護
婚姻して20年経過すると、居住用不動産を配偶者に贈与した場合に贈与税の2000万円までの控除が受けられます。ただ、その後相続が開始した際に、その贈与が「特別受益」として、遺産に持ち戻してそれぞれの相続人の取得分を計算することで、配偶者の取得分が減るという結果になりえることがひとつのネックになっていました。
そこで今回の改正案では、この贈与については原則として遺産に持ち戻す必要は無いとすることが提案されています。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
2018年の民法改正案による相続手続への影響をご紹介します
■はじめに
2018年の3月13日に相続に関する民法改正が閣議決定されました。このことにより、相続に関する分野に大きく影響を与えると考えられています。
そこで、民法改正が行われた場合、相続手続きにいくつか変更がありますので、おおまかに挙げていきます。それぞれの詳細は、今後ご紹介していく予定です。
■相続分野にどのような影響がある?
民法改正により、大きく分けて以下の6つの点について変更が予定されています。
1. 配偶者を保護する権利の設置(配偶者の居住権)
相続開始時に故人と同居していた配偶者が、継続して居住するための権利が創設されます。相続開始により当然発生する「短期居住権」と、遺言や遺産分割で取得できる「長期居住権」の2つがあります。
現在の相続法では、居住権を確保するためには所有権を取得する必要があります。遺産の中で不動産の価値が大きなウエイトを占める場合、居住を継続するために、不動産以外の預貯金などの財産のほとんどを他の相続人に譲らなければならない状況となる事も多くあります。それを緩和する事が創設理由の一つとされています。
2. 遺産分割に関する変更
婚姻して20年以上経つと、居住不動産を配偶者に贈与する場合に2,000万円の贈与税控除があります。ただし、相続が開始して、遺産分割をする場合に、「特別受益」としていったん遺産に持ち戻して各相続人の取得分を計算する事になり、配偶者の取得分が減る可能性がありました。この持ち戻しを必要としないことが提案されています。
預貯金について、遺産分割前でも、相続人に一定金額を仮に払い戻すことを認める制度が創設されます。
3. 自筆証書遺言についての見直し
自筆証書遺言については、大きな見直しが提案されていて、改正されれば今よりかなり利用しやすくなると思います。
まず、全文自筆から、財産目録については、別紙として添付する場合は自筆を不要とする提案があります。そして、自筆証書遺言を法務局で保管する制度の創設が提案されていて、法務局で保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認手続きを不要とする事が提案されています。
4. 遺留分減殺請求についての見直し
現行法では、遺留分減殺請求がなされると、対象となる財産そのもの(現物)を返還するのが原則で、価格弁償が例外的に認められています。これを、完全に金銭請求とする事が提案されています。
5. 相続の効力についての見直し
相続人が、法定相続分を超えて相続財産を取得した場合、その超えた部分の取得を第三者に主張するための対抗要件について、現行法では、「相続させる」との遺言に基づく場合は対抗要件不要とされていて、登記をしないままでも第三者に主張できます。これを、取得方法に関わらず全て対抗要件を必要とする提案がされています。速やかに登記をする必要が出てくることで、登記促進につながる事が期待されています。
6. 相続人以外の親族の貢献についての見直し
相続人が被相続人の療養看護などによりその財産の維持・増加に貢献したと認められれば、遺産分割時に「寄与分」として相続分の上乗せを受けられます。現行法ではこれは相続人だけですが、相続人以外の親族が貢献した場合に、相続人に対して金銭を請求できることが提案されています。
■おわりに
この度の民法改正は、相続・遺言の手続きについて様々な変化をもたらします。
相続トラブルを防ぐためにも、今後の動向をしっかりと確認していく必要があります。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺産相続の相談は誰にする?無料相談ならたかの司法書士事務所
遺産相続を自分で行うのは難しくてできそうもない、と悩んでいる方はいらっしゃいませんか?
相談をするにも誰に何を相談すれば良いかわからないですよね。
スムーズに相続を行うためには、第三者からの的確なアドバイスがあれば安心です。
今回は、遺産相続を相談する専門家についてご説明します。
○相続問題解決のスペシャリスト
遺産相続の専門家には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士がいます。しかし、それぞれの専門家によって得意とする分野が違うため、相談内容によって相談する相手を変えると効果的です。
・弁護士
相続人の間で揉めている場合は、弁護士に相談するのが良いでしょう。調停や審判など裁判所での手続きが必要になった時は弁護士しか代理をすることができません。
また、代理人業務にも対応しているので、生前に弁護士と一緒に遺言書を作成することもできます。
・司法書士
不動産の名義変更が必要になった時は、司法書士に依頼することになります。相続人同士での争いもなく相続税の申告が必要ない方は、司法書士が全ての手続きをすることができるので、相談の費用を抑えることができます。しかし、事務所によっては相続登記しか業務を行なっていないところもありますので、よく調べてから相談すると良いでしょう。
・行政書士
書類を作成する時は行政書士に依頼すると良いでしょう。例えば、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成があります。行政書士は書類作成とそれに関連したアドバイスを行うことはできますが、遺産相続のサポートや実務は一般的には多く行っていません。その分、他の専門家よりも比較的安く相談することができます。
・税理士
相続税の申告をする時は税理士に依頼することになります。しかし、相続したからといって相続税が必ずかかってくるとは限りません。最低で3600万円相当の相続財産がないと相続税の納付義務はありません。
○全ての専門家ができること
上記でそれぞれの専門家が特別に行える業務についてご紹介しましたが、全ての専門家が共通して行える業務として、相続調査と遺産分割協議書作成があります。相続人が誰であるかの調査や遺産分割についての書類を作成したい場合はその専門家でも対応できますので、お近くの相談所や比較的安く相談できるところへ依頼すると良いでしょう。
以上、遺産相続を相談する専門家についてご説明しました。たかの司法書士事務所では、相談の依頼を無料で承っています。不安なことや疑問がある方はお気軽にぜひ一度ご連絡ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言書を作成するべき人とは|万が一の場合に備えましょう
万が一予期せず皆さん自身が亡くなってしまったとき、財産をどのように継続して欲しいか、大切な家族や友人に話しておきたかったことなどを伝えることができません。それを伝えることができる唯一のものが「遺言書」です。
しかし、遺言書を作成することが必ずしも良い結果を生むことになるとは限りません。遺言書の内容によっては、残された家族の気持ちを傷つけてしまうかもしれないのです。
今回は、遺言書を書くべき方や書くことをお勧めする方とはどのような人なのかをご紹介します。
1.相続人がいない方
独身で、親や兄弟、奥様など相続人がいらっしゃらない場合、残された財産は全て国庫に帰属することになります。ある特定の人や団体に寄付したい場合は遺言書に書いておきましょう。
2.子供がいない夫婦の方
遺言書を作成せず亡くなられた場合、亡くなった方の親が存命の場合、2/3が残された旦那様もしくは奥様の相続遺産となります。亡くなった方の親がおらず、兄弟がいる場合ですと、3/4が相続遺産となります。自分の全財産を残された方にどのように配分したいのか具体的に決まっているのであれば、遺言書に書いておきましょう。
3.二世帯住宅に住んでいる方
息子夫婦や娘夫婦と二世帯で住んでいる場合で子供が複数いらっしゃる場合、他の兄弟から法定相続分を主張され、住んでいた家を売却されて財産分割されるケースがあります。また、一緒に住むことで親の世話や介護をしたにも関わらず、遺産相続分の配分に対して不満に思い、子供同士のトラブルが起こることもあります。どの子供がどれだけ配分されるか確認した上で、みんなが納得のいく配分を考えておくようにしましょう。
4.相続財産のうち土地や建物がある場合
土地や住宅は簡単に分割することができず、誰が相続するか?といったトラブルが起きることが多いです。誰に自宅を相続させるのか明確にしておきましょう。子供がいない夫婦であれば、自宅の売却金額を分割するケースがあります。
以上、遺言書を書くべき方や書くことをお勧めされる方をご紹介しました。以上に当てはまる方だけでなく、全ての方に言えることですが、自分の財産を相続させたい特定の方がいらっしゃる場合は、必ず遺言書を書くようにしましょう。思い間違いで、相続させたくない方に相続されることになったり、財産の配分の勘違いがあるかもしれません。たかの司法書士事務所では無料で相談を承っております。ぜひ一度ご連絡ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
不動産相続でお困りの方へ|相続登記の仕方を解説します
「不動産を相続することになったけれど、どうやって相続手続きを行なえばよいかわからない。」
「相続登記ってどうすればできるの?」
このように悩んでいる方は多くいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、相続登記とは何か、どう行なえばよいかといった手順についてご紹介します。
○相続登記とは
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の相続をする時に、その不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きのことです。
遺言書や遺産分割協議によって相続人の財産の取得分が決まりますが、それだけでは遺産を相続されたことにはならないのです。不動産であれば、法務局での名義変更の手続きを行って初めて、その不動産の遺産が相続されたことになるのです。
○相続登記に必要な書類
相続登記の必要書類は主に9つあります。
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
② 被相続人の住民票の除票
③ 相続人全員の現在の戸籍謄本
④ 相続関係説明図
⑤ 不動産所得者の住民票
⑥ 不動産の固定資産評価証明書
⑦ 相続登記申請書
⑧ 不動産の登記簿謄本
⑨ 登記委任状
遺言書や遺産分割協議によって不動産の相続が決まった場合はさらに数枚書類が必要となるので、よく確認しておくとよいでしょう。
○相続登記の期限
不動産登記は基本的に期限が決められておらず、いつでも相続登記を行うことができます。しかし長い間そのまま放っておくと、子供や孫が出産されて相続の権利者が細分化したり、相続者の連絡が取れなくなったりするので、早いうちから済ませておくとよいでしょう。
○相続登記にかかる費用
不動産の所有権や持分権を登記する場合、登録免許税という税金がかかります。登録免許税は固定資産課税台帳価格×税率で算出することができます。
さらに、必要書類を揃えるために1通の発行料金がかかります。相続人が多い場合や相続内容が複雑だったり不動産が自宅から遠い位置にある場合は、自分で書類を揃えるよりも専門家に依頼した方が安くすむことがあります。
○相続登記の申請方法
法務局で相続登記の申請を行なわなければいけませんが、申請する際は法務局の窓口まで出向く方法の他に、郵便で申請する方法とオンラインで申請する方法があります。
以上、相続登記を行う上での主な手順についてご紹介しました。大変複雑な手続きが多いので、スムーズに相続登記を行うためにも専門家に相談するとよいでしょう。たかの司法書士事務所では相談を無料で承っていますので、お気軽にご連絡ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
すぐに開封してはいけません|遺言書の検認について
遺産相続に関して親族間でトラブルが起きることはよくあるケースです。
そして、これを防ぐためにできるのが遺言書の作成です。
もし仮に遺言書が見つかった場合、すぐに開封すると無効になってしまうことがあります。自分の思いや願いを残された遺族に確実に伝えたいですよね。
今回は、遺言書の検認についてご説明します。
○遺言書の検認とは
遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人の立会いのもと、遺言書を開封して遺言書の内容を確認することです。
遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、検認が必要になるのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。公正証書遺言については、公証人の立会いの下で作成しているので、改ざんや偽造される可能性はないので検認する必要がありません。
○検認手続きの流れ
①検認申立書、遺言者の出生から死亡まで一続きになった戸籍等、法定相続人全員の戸籍等の書類を集め、遺言者の最後の住所にある家庭裁判所へ提出します。
②書類に不備がなければ、約1ヶ月から1ヶ月半後に家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する日についてのご案内が送られます。
③遺言書検認日に、申立人は遺言書を持参して、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行います。
④遺言書を検認した後は、遺言書の内容を執行するために「検認済証明書」を発行し、家庭裁判所から書類を返してもらい、遺産相続手続きを行っていきます。
○検認手続きの費用
遺言書1通につき収入印紙代として800円かかります。
裁判所によっては、連絡用の郵便切手が必要になる場合もあります。
○開封してしまった場合
もし誤って開封してしまっても罰金を課されることは滅多にありません。
法律上では5万円以下の罰金を請求されることになっていますが、検認手続きが必要であることがあまり世間一般に広く知られていないため、罰金を課されたケースはあまりありません。
また、遺言書を開封してしまったとしても、遺言書自体の効力や相続人の資格が失われることはありません。しかし、故意に遺言書を開封し、破棄したり改ざんしたり差し替えたりすると、相続人としての権利は失うことになります。
以上、遺言書の検認についてご説明しました。遺言書を見つけたとき、何気なしに開封して読んでしまう方も多いと思いますが、罰金を取られる可能性もありますので気をつけてくださいね。トラブルを未然に防ぐためにも、事前に遺族の方にお伝えしておくと良いかもしれません。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
後悔しない相続放棄|相続放棄のメリットとデメリット
「相続放棄ってなに?」
「相続放棄をするとどうなるの?」
遺産相続は、得となるようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。借金の額があまりにも大きい場合、相続することを放棄することも可能です。
しかし、相続放棄にはメリットもあればデメリットもあります。
今回は、相続放棄をして後悔しないためにも、相続放棄することのメリットとデメリットについてご紹介します。
○相続放棄のメリット
メリット①負債の相続を免れる
被相続人がクレジットカードなどで借金をしていたり、事業で銀行から借入をしていた場合相続人がその返済をしなければいけませんが、その必要が無くなります。また、被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合もそのまま相続されることになるので、その心配もなくなります。
メリット②遺産分割協議に出なくて済む
法定相続人が全員集まって遺産の配分を決める遺産分割協議に出なくて済みます。この協議ではお互いの意見が合わずトラブルになることも多く、ひどい時には裁判所での協議が行なわれることもありえます。多くのお金と時間がかかってしまうことになるかもしれないので、揉め事が嫌いな方や忙しい方は、相続放棄するとよいかもしれません。
○相続放棄のデメリット
デメリット①得となる遺産も相続できない
相続放棄をしてしまうと、すべての遺産に対しての相続できる権利を捨ててしまうことになるので、得となるような遺産も相続できなくなってしまいます。例えば、不動産がある場合や高額な預貯金が残っている場合、負債を超える資産ならば全体として得になるかもしれません。
デメリット②資産が失われる
遺産の中には、先祖代々伝わる骨董品や宝石類、自分が育った家などもあります。相続放棄をしてしまうと、こういった伝統ある品物や思入れある資産も受け取れなくなります。
他の相続人がいる場合、そのまま資産として残すことはできますが、自分しか相続人がいない場合は、相続財産管理人が売り払ってしまい、土地は国ものになってしまいます。
○相続放棄の期限
相続放棄をするか否かを考える期間として熟慮期間が設けられています。この熟慮期間は3ヶ月ですが、特別な理由で3ヶ月以内に決めることができなかった場合、家庭裁判所に対し「熟慮期間延長の申立」を行なえば期間を延長することができます。
以上、相続放棄をすることのメリットとデメリットについてご紹介しました。相続放棄をするか迷ったら一度専門家に相談するとよいでしょう。
たかの司法書士事務所は相談を無料で承っていますので、お気軽にご連絡ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言書を作成したいけれど誰に相談すれば良いかわからない方へ たかの司法書士事務所がお答えします
「遺言書を作成したいけれど、自分で自由に書いたものは有効になるのか。」
「遺言書に何を書けばよいか。」
遺言書を書きたいけれど、自分一人で書くのはちょっと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、遺言書は専門家に依頼して作成することができます。さらに、弁護士だけでなく、司法書士や行政書士にも依頼することができるのです。
そこで今回は、「こんな時、どの専門家に依頼・相談すれば良いのか?」そんな疑問にお答えします。
○財産の中に不動産がある
相続遺産に不動産がある場合は、相続登記に詳しい司法書士に相談すると良いでしょう。
司法書士は、弁護士にも劣らない知識を持っていますので、不動産関係の悩み以外のことを相談することもできます。
○相続税がかかってしまう心配がある
相続税がかかってしまうほどの莫大な財産を持っている場合は、税務に詳しい税理士に相談すると良いでしょう。相続における税務は複雑ですので、遺言書作成時から相続税の生前対策や事業継承まで相談することができます。
○遺産相続に関してトラブルが起きそう
お子様が多数いらっしゃったり、養子がいらっしゃる場合は、遺産分割に関して争いが起きるケースが非常に多いです。そのようなことを未然に防ぐためには、弁護士に依頼すると良いでしょう。
もし仮に遺言内容や相続配分でトラブルが起こったとしても、当事者の代理として交渉することもできます。
○遺言作成から執行されるまで全て任せたい
遺言書作成の依頼を引き受け、執行まで見届けてくれるのが信託銀行です。信頼性が高く、一番身近に感じるのではないでしょうか。
○費用を安く済ませたい
書類作成の専門家である行政書士に依頼すると、比較的安く相談することができます。
○問題は特にないけれど、相談したいことがある
専門家に依頼するほどではないけれど、相談したいことがある場合は、フィナンシャルプランナーに相談すると良いでしょう。
あらゆる面での知識が豊富で、どの専門家に相談すべきかの判断もしてくれます。
○一番おすすめする専門家に相談したい
様々なケースに応じて対応する専門家をご紹介してきましたが、専門家によって大差はありません。
何社かの専門家に相談してみた上で、自分が一番信頼できる専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。
今回は、どの専門家に依頼・相談すれば良いか?についてご説明しました。
たかの司法書士事務所では相談を無料で承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
安心の遺言書作成|遺言書を有効なものにするための方法とは
遺言書は、残された家族に対して自分の思いを伝えることができると同時に、自分の遺産争族を自由に決めることもできる重要な書類です。
しかし、遺言書の書き方は民法で厳密に決められており、自分の希望を書くだけではその希望がそのまま反映させることはできないのです。
そこで今回は、遺言書を有効なものにするための方法についてお話しします。
○遺言書の種類
遺言書の種類には3種類あります。
① 自筆証書遺言
遺言者が紙とペンを使って自筆で遺言書を作成します。遺言者自身がその全文と日付と氏名を書き、これに印を押さなければ有効なものとしてみなされません。
この遺言書には特別な手続きが必要ないため、手軽に作成することができます。
他人に遺言内容を知られることもありません。しかし専門家のチェックを受けていないことで不備があった場合、無効になるリスクもあります。
② 公正証書遺言
2人の証人が立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴きながら書面化して作成します。
公証人が書いた内容を読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認してから署名と押印し、さらに公証人も署名と押印をしなければ有効なものとして認められません。
遺言書は公正証書にして公証人役場に保管されます。
③ 秘密証書遺言
遺言者が自分で用意した遺言書を2人の証人と同行して公正役場に持っていき、遺言書の存在を保証してもらいます。
遺言者と証人と公証人それぞれの署名と押印が必要となります。手続きの際に証人と公証人に遺言書の内容を公開することはありませんが、不備があっても誰にも指摘されないため、遺言内容が無効になってしまうリスクがあります。
○遺言書を書く時の注意点
・せっかく遺産相続について書いていても曖昧な記載だと無効になってしまいます。具体的に正確な内容を書くようにしましょう。
・書き間違いの訂正や内容を追加する場合は、法律が定めた方式があり、守らないと無効になってしまいます。専門家にお願いして訂正するよりも、全て書き直していた方が良いでしょう。
・自筆証書遺言の場合、パソコンは使わず、必ず手書きで書くようにしましょう。手書きでない遺言書は無効になります。
以上、遺言書を有効なものにするための方法についてご紹介しました。自分が亡くなってから、大切な家族や兄弟が自分の遺産の相続に関して揉められるのは避けたいですよね。有効な遺言書を書いて、円満な遺産相続ができるようにしましょう。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。