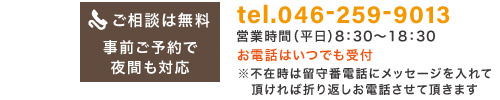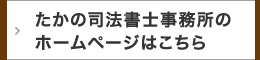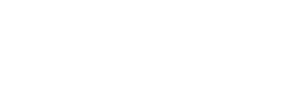Author Archive
相続登記の申請について
不動産を相続して、ご自身で相続登記をしようとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、相続登記についてお話しします。
■相続登記にかかる費用
相続登記を申請する際に、登録免許税を納める必要があります。これが結構な金額になります。
登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%の金額になります。
例えば土地の固定資産税評価額が1,500万円であれば、登録免許税額は6万円になります。
登記申請を行う際に、収入印紙を購入して申請書に貼付けて、納付します。
その他にも相続登記に必要になる書類(戸籍・住民票や登記事項証明書など)を取得する際にかかる費用もあります。
■相続登記に必要になる書類
○登記申請書
法務局の窓口に行くと手に入れることができます。
法務局のホームページからも入手可能です。
○戸籍謄本または除籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本もしくは除籍謄本が必要になります。
それぞれの市区町村の役場で取得します。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要になります。
○住民票の写し
不動産を相続する方については、住民票も必要になります。
○遺産分割協議書
相続人が複数いる場合で、法定相続分とは異なる名義にしたい場合には、「遺産分割協議書」を作成して、相続人全員で実印を押印し、相続人全員の印鑑証明書を付ける必要があります。
他にも、場合に応じて、様々な書類が必要になることがあります。
■専門家に依頼する?
相続登記は、不動産を相続する方自身で手続きすることが可能です。ただ、戸籍などの資料を集めたり、遺産分割協議書を作って他の相続人から印鑑をもらったりなど、慣れない作業に戸惑う方も多くいらっしゃいます。また、法務局や役所など基本的に平日に動かなければならないため、仕事をされている方はなかなか難しいと思います。
そのため、自分でやってみようと法務局に相談にいったものの、断念して司法書士に依頼するという方も結構いらっしゃいます。
司法書士は専門家として日々相続手続きに関わっていますので、ご依頼頂ければ、早く確実に手続きが進むと思います。ぜひご相談ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
自筆証書遺言書を無効にしないために気を付ける作成の5つのポイント
遺された家族がもめないように遺言書を作成したいけど、作成方法が分からないとお悩みではありませんか。
一般的な遺言書(普通方式遺言書)のうち、よく使われているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
公正証書遺言なら、確実に有効な遺言を執筆できるので安心ですが、時間とお金がかかるのが気になるかと思います。
一方で、自筆証書遺言なら自分一人で書けるので手軽ですが、もし内容に不備があり遺言として無効になったらどうしようかと心配されているでしょう。
そこで、ここでは自筆証書遺言を無効にしないために気を付けるべき5つのポイントをご紹介します。
■ポイント1:本文及び日付や署名に至るまで全て自筆で書く
自筆証書遺言では、署名はもちろん、本文や日付も必ず自筆で書かなければなりません。
すなわち、パソコンで作成したものや音声・映像などは無効となります。
また、日付を自筆で書かずに判子を押した場合も無効となります。
■ポイント2:日付や情報を明確に記述する
自筆証書遺言では、作成日が特定できる必要があります。
そのため、「2018年1月吉日」のような日付が分からない表現は無効となります。
■ポイント3:署名・押印をし、封入・封印する
遺言書には遺言者の署名、及びその横への押印が必要です。
署名はペンネームなども認められる可能性がありますが、戸籍通りの姓名を書くのが無難です。私は住所まで書くことをお勧めしています。
判子は認め印でも問題ありませんが、本人が書いたという証明のため、実印を用いるのが最適でしょう。
■ポイント4:加除訂正は決められた方式に従う
自筆証書遺言の執筆にあたって、遺言書への加筆・訂正がある場合には法律で定められた方式によって加筆・訂正を行わなければなりません。
もしその方式を守らなければ、遺言書が無効となってしまうためご注意ください。
そのため、加筆・訂正があるときには全て書き直してしまうのが無難でしょう。
■ポイント5:相続人の遺留分や遺言執行者まで考える
有効な遺言書が書けたとしても、遺留分や遺言執行者のことまで配慮が行き届いていなければ、遺言書通りに遺産分配が行われないかもしれません。
例えば、遺族に法定分とは異なる相続分を指定したいとしても、法定相続人が遺留分減殺請求によってあなたの決めた遺産分割に抗うかもしれません。
このときには、遺産分割だけでなくこのような分配にする理由・心情なども記しておく方がよいかもしれません。
また、遺言内容に認知や推定相続人の廃除が含まれる場合には遺言執行者が必要となりますのでご注意ください。
自筆証書遺言を法的に有効にする・遺族に認めてもらうためにはこれらの注意が必要です。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言を無効にしない公正証書遺言の作成方法とは
「自分が亡くなった後のために遺言を残しておきたい。でも、法的に有効な文書が自分で書けるかどうか心配だ…」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
遺言書は、正しい書き方に従っていれば、自分一人で書いたものでも遺言書として効果を発揮します。
しかし、書き方を間違えて法的な有効性を欠いてしまうと、せっかくの遺言書が無駄になってしまいます。
そのような心配をされている方は、公正証書遺言を利用することをおすすめします。
公正証書遺言なら、公証人が立ち会う中で遺言書を作成するため、法的に有効な遺言書を遺すことができます。
そこでここでは、公正証書遺言とは何か、作成するにはどうすればいいのかをご紹介します。
■公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人2人の立ち会いのもとで執筆する遺言書のことです。
基本的には、遺言書を遺したい人が公証役場に行きますが、寝たきりで動けないなどの理由がある場合には公証人に出張してもらうことも可能です。
■公正証書遺言を作成する方法
公正証書遺言作成手続きの流れは以下の通りです。
1.遺言書作成の目的・内容について本人の考えを整理する。
まずは、遺言書を遺すご本人が、何のために・誰のために遺言書を遺すのか考える必要があります。
遺言書でできるのは、財産を特定の相続人に相続させること・遺産分割の割合を指定すること・相続人以外の第三者に財産を遺すこと・遺族にメッセージを遺すこと・遺族の相続手続きの負担を軽減することなどです。
これらを踏まえたうえで、なぜ遺言書を遺すのかを考えましょう。
2.基礎資料の準備
基礎資料とは、印鑑証明書・遺言者と相続人の続柄の分かる戸籍謄本・相続不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書・証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものです。
証人については、信頼のおける友人でも構いませんが、心当たりがない、あるいは秘密を守ってくれるか不安な場合は、守秘義務のある法律の専門家に依頼するのがおすすめです。公証役場で紹介してもらうこともできます。
3.公証人との事前打ち合わせ
本人の居所から最寄りの公証役場に上記の資料を持参して、遺言の内容や手数料などについて公証人と打ち合わせします。
もしくは、公証人でなくても他の法律の専門家にも相談できます。
そのとき、専門用語が飛び交うかもしれませんが、分からないことは遠慮せず尋ねてください。
4.証人2人の立ち会いの下、公証役場で証書を作成
遺言書作成の当日、本人と証人2人が公証役場に訪れます。
作成時は、公証人が本人と証人2人の前で遺言書を読み上げます。
問題が無ければ本人と証人2人が署名・押印し、これで遺言書の完成です。
公正証書遺言の作成には、労力とお金が必要ですが、その代わりに確実に効力のある遺言書を作成することができます。
安心して遺言書を遺したいなら、公正証書遺言がおすすめです。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
専門家に任せてしまいたい面倒な相続登記とは
「不動産の相続登記をしなければならないけど、手続きって何をすればいいんだろうか。」とお悩みではないでしょうか。
相続により不動産の名義を変更するには、登記手続きが必要です。
そこで、ここでは登記の方法や必要な書類について少しご紹介します。
詳細なことは複雑で状況によって変わるため専門家に相談するのがおすすめですが、相談前にこれを読めば、話も理解しやすく相談もスムーズに行くかと思います。
■相続登記をする方法
相続登記をするには、登記申請書に、必要書類を添付して、法務局に提出する必要があります。
登記に必要な書類には大きく3種類あります。
1つ目は、被相続人と相続人の相続関係を示すための書類です。
これは、被相続人の戸籍除籍・改製原戸籍、相続人全員の戸籍や相続関係説明図があります。
このうち、被相続人の戸籍除籍は亡くなった時点でのものだけでなく、生まれてからの除籍・改製原戸籍を全て収集しなければなりません(ただし、公正証書遺言による場合は最後の戸籍除籍だけで可)。
これは、相続関係説明図に記載された者が相続人の全員であることを証明するためです。
2つ目は、固定資産評価証明書です。
固定資産評価証明書とは名前の通り固定資産の評価額を証明したもので、登記手続きで支払う登録免許税を算出するために用いられます。
3つ目は、登記原因証明情報です。
「登記原因証明情報」という名前の書類はなく、相続の仕方によって提出すべき書類が変わってきます。
有効な遺言書に基づいて遺産相続が行われた場合、遺言書が登記原因証明情報となります。遺言が無く、遺産分割協議を行って遺産の分配を定めた場合には、遺産分割協議書が登記原因証明情報となります。法定相続分通りに登記をする場合は、戸籍謄本等と相続関係説明図自体が登記原因証明情報となります。
必要な書類が全て揃えば登記が完了し、登記識別情報(昔の権利証)がもらえます。
書類に不備があれば、法務局から電話連絡がきますので、訂正をしに再度法務局に出向く必要があります。
法務局は平日しか空いておらず、必要書類の多くは役所で取得するため、平日に動く必要があります。
平日は仕事でなかなか動けないという方は、専門家に依頼するのが良いかと思います。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続登記に必要な費用と書類について簡単解説
相続登記とは、相続した不動産の名義変更を行う手続きのことです。
これには、費用や様々な書類が必要となります。
そこで今回は、相続登記に必要な費用と書類についてご紹介します。
■登録免許税
相続登記をするには、登録免許税という税金を納める必要があります。
登録免許税は、法務局や郵便局などで収入印紙を購入してその収入印紙を登記申請書に貼り付けて納めます。
登録免許税額は、不動産の固定資産税評価額×0.4%です。
例えば、土地と建物合計で2,000万円の評価額であれば、登録免許税額は80,000円になります。
■司法書士報酬
相続登記の手続きは自分でも行えますが、書類の収集や作成の面倒は避けたい、平日に法務局へ行く時間がなかなか取れないという場合、司法書士に依頼するのが良いでしょう。
相続登記の司法書士報酬は特に規定はなく自由化されています。詳細は司法書士に確認するようにしましょう。
次に、ご自身で登記申請することを想定して、相続登記に必要な書類をご紹介します。
■登記申請書
相続登記は法務局に申請書を提出して行います。法務局へ相談に行くとひな形をもらえます。
なお、法務局の相談は、事前の電話予約が必要です。
■相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局で取得します。不動産の地番や家屋番号が分かれば、どこの法務局でも取得できます。登記申請書には、登記事項証明書の記載通りに不動産の表示を記載する必要があります。
■被相続人の住民票の除表票
住民票に、被相続人が亡くなった旨の記載がされたものです。
相続人であれば故人の最終住所の市区町村の役場で取得できます。
■被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式
被相続人の法定相続人を確定するために必要な書類です。被相続人の出生まで遡って、除籍謄本や改製原戸籍謄本を取得する必要があります。
被相続人が本籍を何度も変わっている場合は取得がかなり面倒になります。
■相続人全員の現在の戸籍謄本
各相続人の本籍地をの市区町村役場で取得できます。
■遺産分割協議書もしくは遺言
その不動産をどの相続人が相続するのか。それを明らかにするため、遺言書か、遺産分割協議書が必要になります。相続人がそもそも一人だけの場合は不要です。
遺言書は、遺言公正証書の正本か、検認済みの自筆証書遺言が必要です。
遺産分割協議書は、その不動産を誰が相続するのか記載されたもので、相続人全員の実印が押印され、全員の印鑑証明書が付けられたものが必要です。
法務局に相談するとひな形をもらえます。
以上、相続登記に必要な書類をざっくりですがご紹介しました。
他にも必要となる書類がある場合もありますので、法務局や司法書士に相談して下さい。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言書の検認の必要性について簡単解説
自筆の遺言書は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認手続きを経ないと、各種の相続手続きに使うことができません。
今回はそんな、遺言書の検認について簡単にご紹介します。
■遺言書の検認について
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が、家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
すべての遺言書に検認が必要な訳ではありません。自筆証書遺言と秘密証書遺言に必要な手続きです。
遺言公正証書は検認手続きを経ることなく、すぐに相続手続きで使用できます。
■遺言書の検認をする目的
遺言書の検認は、相続人に対して、遺言の存在およびその内容を知らせるとともに以下の内容を確認する意味があります。
・遺言書の形状や加除訂正の状態
・日付、署名
検認日時点での遺言内容を明確にし、偽造や変造をされていないか確認し、それ以降の変造を防止するための手続きとして必要なものとされています。
あくまで確認と変造の防止が目的のため、遺言内容の法的有効性を判断する手続きではありません。
■検認の必要性
遺言書の検認手続きをせずに遺言内容を実行した場合は5万円以下の過料が科せられます。封印された遺言書を検認手続き前に開封したときも同様です。
ただそもそも、不動産登記手続きでも、預貯金や株などの相続手続きでも、検認済みの遺言書でなければ使用できません。
遺言書の検認手続きには、様々な必要書類があり、費用もかかります。
不安な場合は、司法書士に相談してみてください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続登記をするべき理由について
相続登記を放置すると、相続した資産を失ってしまうかもしれません。
そのようなことがないように、正しい知識をつけておく必要があります。
そこで今回は、相続登記についてご紹介します。
■相続登記について
相続登記とは、簡潔に言うと、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を、相続人に書き換える作業をいいます。
■相続登記の期限
相続登記に期限はありません。相続登記は義務ではなく権利だからです。
相続登記をしないことで発生するデメリットについては以下に解説します。
■相続登記(そのための遺産分割協議)をしないデメリット
・相続人が増えて遺産分割が困難になる可能性
名義人が亡くなってから、相続人に名義を変えるまでは、不動産は相続人全員の共有状態になります。そして、相続人の一人さらに亡くなると、相続人の相続人にまで共有されるのです。
登記するには相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書が必要なため、相続人の人数が増えると、なかなか合意に至らず登記することが難しくなる可能性もでてきます。
・認知症による影響
相続登記を放置している間に、相続人の一人が認知症などで判断能力が低下してしまうと、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任しなければ、遺産分割協議をすることができなくなります。
・連絡がつかない者が出た場合
相続登記を放置している間に、相続人の一人の行方が分からなくなり音信不通となった場合、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任してもらうなど、面倒な手続きが必要となります。
■相続登記の方法
相続登記の申請は法務局で行います。不動産所在地を管轄する法務局に申請します。登記手続きはご自分でもできます。
ただ、書類に不備がある場合など、何度か法務局に出向かないといけなくなります。
なかなか平日に時間が取れない、面倒なことは避けたいという場合には、司法書士に依頼した方が良いでしょう。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
無効にならない遺言書の作成方法について簡単解説
遺言書は誰でも簡単に書くことができますが、ルールに則って書かないと無効になってしまいます。
そこで今回は、無効にならない遺言の作成方法についてご紹介します。
■正しい自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方は簡単ですが、法律に定められた要件や形式が存在し、それぞれの要件や形式を満たす必要があります。
要件や形式に不備があるがために自筆証書遺言が無効になってしまう事例は結構あります。
そうなってしまうと、自分の思い通りに遺言が執行されなくなってしまいます。
そのため、不安要素がある場合は司法書士などのプロに相談するようにしましょう。
■自筆証書遺言書を作成する上での最低限のルールについて
・遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する
パソコンに打ち込んだ物や、代筆してもらったものは無効です。また、音声、ビデオによるのも無効です。
・日付を明記する
作成日を正確に明記してください。確認できない場合無効となります。また、スタンプも無効です。
・署名・押印する
氏名だけで可ですが、住所も書いた方が良いと思います。
また、押印は認印で可ですが、確かに本人が書いた証明として、実印を用いた方が良いと思います。
・加除訂正はルール通りにする
書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。
訂正や追加がある場合は、全て書き直すのが無難です。
・その他の注意点
「遺言の記載内容は具体的に書くこと」
「不動産は登記簿謄本通りに記載した方が良いこと」
「預貯金は金融機関の支店名、預貯金の種類や口座番号まで記載すること」などがあります。
詳細まで記載するようにしましょう。
遺言書が効力を持つのは書かれた方が亡くなってからなので、手違いがあっても正すことができません。
きっちりとルールに従って書くようにしてください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
最も用いられる遺言方法「普通方式遺言」について解説
遺言は法律によって普通方式の3種類、もしくは特別方式の2種類のいずれかを用いて作成することが定められています。
そのため、しっかりとルールに則った方式で遺言を書かなければ無効になってしまいます。
そこで、今回は通常の遺言作成でよく用いられる「普通方式遺言」の3種類についてご紹介します。
■普通方式遺言について
遺言には、大きく分けると普通方式の遺言と、特別方式の遺言の2つの方式があります。
ここでは、普通方式遺言の3つの種類についてご紹介します。
■自筆証書遺言について
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を明記し、押印して作成する遺言形式です。
筆記具と紙さえあればいつでも作成が可能ですので、他の方式と比べて費用がかからず手続きも簡単に行うことができます。
また、自分一人で作成ができますので遺言内容を他人に秘密にすることができます。
しかし一方で、内容を専門家にチェックしてもらうことがありませんので、法的要件不備のために無効となるリスクが存在します。
さらに、紛失や偽造、隠匿の心配や遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題も挙げられます。
■公正証書遺言について
公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管する遺言方式です。
作成に専門家である公証人が関わるため、法的に最も安全・確実な方法といえ、後日の紛争防止のためにも最もおすすめできる選択肢です。
その分費用がかかりますが、将来の相続手続きの際にも、自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認手続きが不要で、受遺者にとって手続きが楽にできるというメリットがあります。
■秘密証書遺言について
遺言者が作成した遺言書に自署・押印した上で封印し、公証役場に持ち込み公証人および証人立会いのもとでさらに公証役場の封筒に入れて封印します。
遺言内容を誰にも知られずに済み、偽造防止にもなります。
しかし、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけにはいかないので不備があれば無効になってしまいます。また、費用もかかります。
遺言書に法的な不備があったり、表現が足りないことで相続人同士のトラブルにつながったりすると、遺言の執行が難しくなります。
そのため、遺言に関する知識をしっかりとつけた上で方式を選ぶようにしてください。
遺言書の作成には色々な方法がありますが、それぞれメリット・デメリットが存在します。
後々のトラブルを避けるためにもご自身・ご家族の望む遺言方式で書かれることをおすすめしますので是非参考にしてください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言作成にあたって司法書士に相談するメリット
遺言は法律の専門家に頼まなければいけないという決まりはありません。
法律に定められたルール通りに書けば有効な遺言書を残すことができます。
そのため、ご自分で遺言書を書かれる方もいらっしゃいます。
しかし、それが思わぬ形でトラブルを引き起こしてしまうケースもあります。
そのため、今回は司法書士のような法律の専門家に依頼するメリットについてご紹介します。
■無効にならない遺言書が書ける
遺言書を書いても、法的に無効と判断されれば意味がありません。
そのため、司法書士など専門家に相談して遺言書を書くようにすれば、無効な遺言になってしまうリスクを避けることができます。
また、無効にならなくても正しい表現ができておらず複数の解釈が可能になると、後々トラブルを引き起こしてしまいます。
ご自分で書いた遺言書が本当に、望んでいる通りの結果を得られるのかプ司法書士など専門家に相談すれば正しい法的効果を生じる遺言文案を教えてもらえます。
■しっかりと遺言執行できる遺言書が書ける
遺言書は書くだけでなく、財産の相続手続きができていなければなりません。
法律手続きができてはじめて遺言書が意味をなします。
遺言執行がしっかりとできる内容の遺言書になっているか相談しておくことをおすすめします。
■遺言書作成の文案を作ってもらえる
司法書士など専門家に遺言書の相談をしても、自筆証書遺言を書くのはご自分です。
しかし、文案は司法書士など専門家が提案してくれます。その内容に納得がいけば、あとはご自分の手書きでそのまま転記すれば遺言書が完成します。
■色々な相談ができる
遺言書の作成だけでなく、他の法律問題や法的手続きも相談することができます。
例えば、不動産などの生前贈与や、認知症に備えて任意後見契約の締結、死後事務委任契約の依頼などです。
司法書士は遺言書の作成以外にも色々な日常生活の問題を取り扱っているため、日頃の疑問も相談できます。
司法書士など専門家は必要であれば遺言書の保管もしてくれます。
また、遺言書を書いた後でも、何か法律関連で困ったことがあれば相談に乗ってくれます。
ルール通りに記載されていない遺言書は意味を持たないため、相続人の間でトラブルを引き起こします。
そのため、費用はかかりますが、安全に法的効力のある遺言書を作成するためにも是非、司法書士など専門家に相談してみてください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。