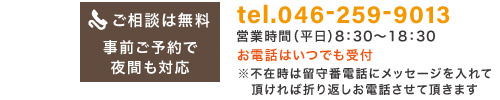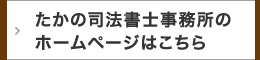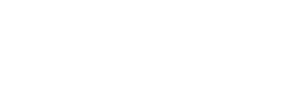Author Archive
遺言書の作成時に気をつけたい、遺言が無効となる4つの事例
高齢社会の到来に伴い、遺言を書かれる方も増えています。ただ、遺言書に触れたことがないという人が大半のはずですので、書き方や形式、書く内容すらも何から書けばいいのか、と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
そのような方に向けて、今回は遺言書が無効になってしまいがちな4つの事例をご紹介したいと思います。
1.パソコンやワープロで書かれている
自筆証書遺言を残そうとお考えの方は、署名だけでなく、遺言内容も全文が自筆(後から消すことができない筆記用具による)でないと遺言書として認められません。
パソコンで作成したものに署名と捺印があったとしても、遺言書としては認められないため注意してください。
2. 押印がない
押印も1と同様に必須です。署名か押印どちらかがあれば良いと考えがちですが、どちらも必須で必要ですのでお気をつけください。
3. 日付の記載がない、特定できない
また、その遺言をいつ書いたかも必ず記載してください。もちろん日付の記載も自筆である必要があります。
また、「2017年8月某日」などと、特定の日付がわからない書き方をした場合には無効となってしまうため注意してください。
4. 2人以上の共同で書かれた遺言書
いくら親密なパートナーといえど、2人で協力して書いたものは自筆証書遺言にはなりません。
基本的に、1人の手によって最初から最後まで書かれている遺言書のみが自筆証書遺言として有効です。夫婦で作成する場合は、それぞれ1通ずつ書く必要があります。
いかがでしょうか。
今回、失敗しがちな4つの事例をご紹介しました。これ以外にも遺言を書くときに気にしなければいけないことがあります。
もし不安を感じる方は、ご気軽にたかの司法書士事務所までご相談ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
不動産の相続登記をしていないため困る場合
「親が残した不動産や土地を相続したいが、その際に必要な手続きがわからない。」という方や、「相続の手続きが面倒臭い。」という方がいらっしゃると思います。
しかし、だからと言って手続きを放っておくと、困ったことが後から出てくる可能性もあります。
そのような事態に陥らないためにも、今回は、相続登記を放置していたがための困ったことを少しご紹介します。
■不動産を売却したくてもできない
「親が所有していた土地建物を売却しよう。」
ご両親ともに亡くなり、自分も兄弟姉妹も持ち家に住んでいるため、ずっと誰も住まないまま放置していたが、建物の劣化も進んできたので売却したいという場合が、最近増えてきています。
土地建物を売却するには、必ず相続登記を行う必要があります。相続登記を経なければ売却はできません。
ご両親が亡くなった時であれば相続人で遺産分割協議がすぐできたはずなのですが、放置している間に、相続人である兄弟姉妹の一人と音信不通になったり、相続人の一人がその後亡くなり、その相続人が協議に応じないといった事情が生じてなかなか売却に至らないという事も実際にあります。
■遺産分割協議のタイミングを逃し、話がこじれる
財産や現金の配分というのは、比較的すぐに話をするものです。不動産は簡単に切って分けることができないため、なんとなく後回しにしてしまい、いざ協議をしようとしたときに、売りたい売りたくないなど、実はそれぞれの考え方が違って、揉め事が起こってしまうケースもあります。
遺産については、一部の財産だけをとりあえず分けるのではなく、最初に全てについて話し合って分ける方が断然お勧めです。
■余計な手間や時間がかかる
長年経ってから相続登記を行うと、役所の書類の保存期間の関係で取れない書類がでてきたり、法定相続人が増えてしまったりなど、余計な手間がかかることが多くあります。
いかがでしょうか。
相続登記には特に期限がないため後回しにしてしまいがちですが、このように、相続登記の手続きをしておかないと、後からトラブルや困ったことが続々と起こってしまう可能性があります。
もし、お困りのことがありましたら、たかの司法書士事務所まで、お気軽にご連絡ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
相続の登記を自分で行う際に必要な手続きをご紹介します
相続の手続きを行う際に、年金など役所の手続き、銀行預金などの手続き、不動産の名義変更などにつて、できる限りは自分で行いたいとお考えの方もいらっしゃいます。
そこで今回は、相続登記をご自身で行う際の一連の流れをご紹介します。
■調査と相談
やはり、最初はインターネットでの検索や相続登記の本を読むことから始める方が多くいらっしゃいます。
しかし、特にインターネットは情報が多すぎて、これらに載っている情報の中でもどれが本当に自分に必要なのかわからないという方も多く、実際に法務局に行って相談をされる様です。
■被相続人と相続人全ての戸籍謄本を収集
まずは、相続にまつわる人全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を集めます。誰が相続人かを特定するため、相続に関するどの手続きでも必要になります。
近くの市役所で全て揃えば良いのですが、地方の実家にいた頃の改製原戸籍謄本を郵送で取り寄せるという場合には、申請書をダウンロードして小為替と返信封筒を入れて郵送するなど、これが結構面倒な作業となります。
■遺産分割協議書を作成
次に、相続人間の協議で不動産を誰が相続するかを決定し、遺産分割協議書として書面を作って、相続人全員で実印を押印し、印鑑証明書を付けて登記申請時に添付する必要があります(ただし、遺言書があれば遺産分割協議書ではなく遺言書を添付します)。
なお、相続人間で揉めてしまい協議がなかなかできない様な場合は、家庭裁判所の調停を利用したり、法定相続分で全員の共有で登記をするという事になってきます。
■固定資産評価証明書を取得して登記申請
上に述べた書類を完成させたのち、相続登記の際に納めなければいけない税金(登録免許税)を計算するため、固定資産税評価証明書という書類も登記申請の際に添付します(ただしこの扱いは法務局によって異なります)。固定資産税評価証明書は、市役所の資産税課で取得できます。
登録免許税額は、相続登記については、固定資産税評価額の0.4%です。
登記申請書を作成して、不動産を管轄している法務局へ赴き、今までに集めた書類と登録免許税分の現金を提出します。
かなり大雑把ではありますが、このような流れで登記申請を行います。
いかがでしたか。
役所あいての手続きのため、平日に限られ、お仕事をされている方はなかなか手間取ってしまう事も多いようです。
このような手続きを任せたいとお考えの方は、たかの司法書士事務所にお問い合わせください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言書は司法書士や行政書士など専門家に相談
遺言書を書こうと考えだして、いざ書こうとなっても、何から始めたらいいのか、どういう風に書いたらいいのか分からないという方も多いと思います。
そのような方々におすすめしたいのが、司法書士や行政書士など専門家に相談することです。
・遺言書の書き方には決まりがある
遺言書の書き方は自由ではありません。民法で厳格にその方法が定められています。
何も調べずに遺言書を書いてしまうと、その遺言書が無効になってしまうこともあります。
しかし、自分で書き方を調べながら書くのは、いろいろな箇所で疑問や不安が沸き起こり、結構手間のかかることです。
司法書士や行政書士など専門家に相談すれば、遺言者の考えを正確に実現させるための書き方をお伝えすることができます。
・遺言書の文案作成もしてもらえる
自筆証書遺言書は遺言者自身が書かなければなりません。専門家に相談したとしても、それは変わりません。
しかし、専門家に文案を作成してもらうことはできます。
できた文案を一言一句書き写せば、問題なく遺言書を完成させることができます。
・遺言書の保管も依頼できる
遺言書が完成しても、保管場所をどうするかという問題が残っています。
受遺者(もらう人)に託しておくのが一番確実なのですが、自分が亡くなるまでは身内に見せたくないという場合、机の引き出しにしまっておく人もいるでしょうし、誰にもわからないような場所に保管しておく人も多いと思います。
しかし、亡くなった後に遺言書が見つからない事態になってしまっては本末転倒です。
その様な場合に、第三者である司法書士や行政書士など専門家に、遺言書の保管を託すのも一つの方法です。
・遺言執行の依頼もできる!
特に受遺者が相続人以外の方の場合、遺言執行者を定めておかないと、本来の相続人の印鑑が必要になるなど面倒な手続きになってしまう場合もあります。
受遺者の方を遺言執行者にすることができますが、受遺者の方に手続きの負担をかけるのも申し訳ないという方もよくいらっしゃいます。
そのような場合、司法書士や行政書士など専門家に遺言執行まで依頼することもできます。
専門家であれば、遺言書の内容を確実に実現させられます。
遺言書を書くことは人生で何度もありませんので、詳しい知識を持っている方はほとんどいらっしゃいません。
その知識を持っていて、確実に遺言者の考えを実現できるのは、司法書士や行政書士などの専門家です。自分で調べるのは手間がかかる、面倒な手続きを全て任せたいという方は、ぜひご相談ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言の作成方法-正しい自筆証書遺言の書き方-
「自分が子孫に残せるものは何かな」とお考えの方。遺産相続にあたっては、その多少に関わらず、親族の間に遺恨を残すこともあります。そのような場合、遺言書が遺されていれば防げたであろうと感じる事も多くあります。
もし、事前の準備次第でそのようなことを防げるのであれば、それに越したことはありません。
そのためにも、今回は遺言書の中でも最も手軽に作成できる「自筆証書遺言書の書き方」をご紹介します。これを参考に、自らの遺産や遺言について考えてみてください。
■正しさを担保する6つのステップ
自筆証書遺言書を作成する場合、有効に認められるために5つほどの確認すべきことがあります。
1.遺言の内容、日付、署名など全てを自筆すること
たとえ本人の意思が反映されているといっても、他者代筆やパソコンなどで作成されたものは有効な自筆証書とは認められません。音声やビデオについても同様です。
2.日付を明記する
2017年某日や、7月、などと特定の日が分からない日付の書き方はNGです。
また、日付を表すスタンプもNGです。日付も自筆である必要があります。
3.署名と押印をする
自分のフルネームを署名した後、押印して完了です。押印が無いと無効です。
押印は認印でも構いませんが、自ら作成した証明としては実印の方が好ましいと思います。
4.加除訂正に注意
書き間違い、書いた内容に付け足したいという場合、加除訂正方法が民法で厳格に定められていますので、全て書き直されることをお勧めいたします。
5.不動産や預金口座など、遺産は具体的に記載する
相続財産を特定できない曖昧な表現を使うと、場合によっては効力が認められない事も生じえます。またご子息たちも困ってしまいます。
なお特定せずに、「全ての財産」をAに、とかAとBに半分ずつといった記載でも構いません。
いかがでしょうか。
この記事を参考に、今後の自分の将来設計について考えてみてください。
ご不明の点などあれば、いつでもたかの司法書士事務所までお問合せ下さい。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
秘密証書遺言の作成の仕方
遺言を作成したい方々の中で「出来れば生きている間は、その内容を誰にも知られたくない。」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような場合に利用できるのが、「秘密証書遺言」です。
この遺言は、内容を誰にも知らせずに秘密にしたまま、公証人に遺言書の存在のみを証明してもらう物です。
あまり利用されることはないのですが、一応、その使い方を知ってもらうため、今回は「秘密証書遺言」について、その作成方法をご紹介します。
■遺言書の作成
まずは、遺言者が自分で遺言書を作成します。
「自筆証書遺言」と異なるのは、手書きでなくワープロやパソコンで作成しても構わないというところです。また、「公正証書遺言」と異なり、遺言書の作成を一人で行えることも、この遺言の特徴の一つと言えるでしょう。
最後に署名と捺印、そして日付を入れるのを忘れないでください。内容はパソコンで作成できますが、署名は自筆である必要があります。
遺言ができたら、封筒に入れて封印をしましょう。その際には、遺言書に捺印した印をお使いください。
■遺言書の提出
次に、先ほど封をした遺言書を公証人と証人の2人以上の前に提出します。
この際、自己の遺言であることを申請し、氏名と住所と一緒に提出すれば申述が完了です。
■公証人が封筒を確認
公証人が、その遺言を提出した日付、遺言の申述内容を封筒に記載して署名と捺印をします。
その他にも、証人と遺言作成者本人も封筒に署名と押印をして、一連の手続きは終了です。
■家庭裁判所の検認
この遺言書の作成自体には、公証人が関与していないため、家庭裁判所での検認を行う必要があります。この際、秘密証書遺言は必ず封をされているはずです。検認の期日に、家庭裁判所で開封することになります。
いかがでしたか。
秘密証書遺言についての作成方法をお分りいただけたでしょうか。
作成段階では、自筆証書遺言や公正証書遺言よりも簡単なのがこの遺言の特徴ですが、家庭裁判所での検認が必要という点と、遺言内容自体に専門家が関与しないため、不備による無効の危険がある点で、あまり利用されないのかもしれません。
もし、興味がある場合には、たかの司法書士事務所にご相談ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言書の検認を行う前に知っておくべき3つのこと
「親や親族の遺言書を預かっているけど、これからどのようにしたらいいかわからない。」
「噂で裁判所での検認が必要ということは聞いたけど、どのようなものかわからない。」
というようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃるでしょうか。
検認というのは、家庭裁判所において、その遺言書がたしかに本人によって作成されたものかどうかを、相続人が集まって確認する作業です。
裁判所と聞いて、ハードルが高い作業のように感じてしまうこともあるかもしれません。
その壁を取り除くためにも、今回は、裁判所で検認をする前に知っておくべき3つのことをみなさんにご紹介いたします。
■検認の目的
では、そもそもなぜ検認を行うのでしょうか。
第一の目的は、家庭裁判所と相続人とで、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付・署名を確認して、その遺言書が偽造されたものではなく、本当に有効性があるかどうかを証明するとともに、その時点からの変造を防ぐというものです。
第二の目的として、検認手続きを通して、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせることがあります。
検認手続きが無いと、相続人の一人が偽造した遺言書で、他の相続人の知らない間に名義変更などを行うことが可能となるので、それを防ぐことを目的としています。
注意が必要なのは、検認手続きは、遺言自体の有効・無効を判断するものではない事です。遺言自体の有効性に問題ある場合は、別に裁判などで争う事になります。
■検認が必要となる遺言書
遺言書の中には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言という3つの種類があり、その中で検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つのみです。
公正証書遺言の作成方法をご存知の方はすでにお気づきかと思いますが、この遺言は作成時に公正役場の公証人と証人2人が立ち会いますので、偽造や変造の可能性がないため、検認の必要がありません。
■検認の流れ
検認の一連の流れは、遺言書を保管してる方が、遺言書検認の申立てをするところから始まります。
この申立ての先は、遺言者の最後の所在地を管轄する家庭裁判所であり、保管者の住所には関係がないため注意をしてください。
次に、家庭裁判所から、相続人全員に対して、検認の日を指定する「検認期日通知書」が送られてきます。検認期日に家庭裁判所へ行くか否かは各相続人の自由です。最低限、申立人一人が出席すれば手続きは進みます。
そして検認当日、無事に検認が終わると、裁判所からの「検認済証明書」が合綴された遺言書が返却されます。
この証明書には、「この遺言書は平成○年○月○日に検認されたことを証明する。」などという一文が付されています。
いかがでしたか。
少し理解しにくい部分があれば、お近くの司法書士などの専門家にご相談のうえ、大切な遺言書の手続きを進めてください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
一番確実な遺言、公正証書遺言の作成方法をご紹介します。
遺言を作成しようかとお考えの方々にお勧めしたい、一番確実な遺言の残し方が「公正証書遺言」です。
この公正証書遺言は、遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成するというものです。
不備などが起きる可能性がない点が一番の魅力といえるでしょう。
今回は、そんな公正証書遺言の作成方法を細かくご紹介していきたいと思います。
■必要なものは?
この公正証書遺言に必要な書類は以下のようなものです。
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者の戸籍謄本
・受遺者(もらう人)の住民票、戸籍謄本
・固定資産税評価証明書
・不動産登記簿謄本
など
これらを揃えた上で、公証人と証人2人に、遺言の内容を口頭で話していきます。
このとき、未成年者や遺言者の推定相続人と受遺者、それらの配偶者や直系親族は証人となることができないのでご注意ください。
また、何らかの事情により口頭で話せない場合には、遺言者が筆談などを利用して、公証人に作成してもらうことができます。
しかし、自分で判断する意思能力を認められない者が遺言を作れません。そのような方は残念ながら、公正証書遺言に限らず全ての遺言を作成することができません(作成しても有効ではありません)。
■事前の準備が必要
いくら専門家である公証人とはいえ、突然書類を持参して来られてすぐにその場で作成するというのは困難です。そのため、遺言者は事前に遺言内容の打ち合わせを公証人とする必要があります。
そして遺言書作成の当日は、その内容を確認しながら読み合わせるという作業になります。
■遺言が作成できたら
証人の立会いのもと、公正証書遺言の内容を確認したら、遺言者と証人がそれぞれ署名と捺印をします。そして最後に、公証人が署名捺印して遺言書の完成となります。
ここで大事なのは、この遺言の原本が公証役場に保管されるということです。
これは紛失や改竄の心配がなく安心できるポイントです。
また、遺言者にはその正本と謄本が交付されます。万が一紛失してしまった場合、謄本を再発行してもらうことができます。
いかがでしたか。
公正証書遺言というのは、費用はかかりますが、遺言作成方法の中でも確実性では優れています。
その遺言の作成方法がこの記事を通してご理解いただけたら何よりの幸いです。
もし、こうした遺言を残すことに興味のある方は、ぜひ一度「たかの司法書士事務所」にお問い合わせください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺産相続の際に親の借金が判明した場合の三つの対処法
「親が亡くなり、遺産を調べていたら借金のあることが発覚。これは自分が引き継がなければならないのか?」
同居していた場合はあまり無いと思いますが、別居していた場合には思わぬ負債が発覚することがあります。
親の借金は、生前は子には関係ないのですが、亡くなると相続により子が引き継ぐ事になります。
相続すべき遺産に借金が含まれていた場合にどのように対処すべきかについて正しい知識を持っておくことが重要になります。
今回は、親の借金についての三つの対処法をご紹介します。
◇対処法①:親が自己破産する
これは相続に至る前、親の生前に多額の借金があることが発覚した場合の対処法です。
裁判所で支払い不能の宣告と免責を受けることによって、返済義務がなくなるものです。相続人である子ではなく、借金のある親本人に行ってもらう必要があります。
ただし、自宅不動産を所有している様な場合は、これを手放す必要があり、手続きも複雑になりますので、個人再生や任意整理など他の方法も考える必要がでてきます。
◇対処法②:相続放棄する
相続放棄とは、相続人となる地位の一切を放棄するもので、マイナスの財産はもちろんプラスの財産も全て放棄することになります。そのため、明らかにマイナス分が多くなる場合には相続放棄の選択が有効です。
なお、相続放棄を選択する際に要注意なのは、申告期限です。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」というように法律上で定められています。できるだけ早く裁判所で手続きをしないといけないということを覚えておきましょう。
また、もう一つ要注意があります。親の借金の連帯保証人になっていた場合、相続放棄は無意味になります。親自身の負債の相続はしないものの、自分自身の保証人としての支払い義務は残るのためです。もし仮に連帯保証人になってまっていた場合は、金額などにもよりますが、相続放棄ではなく次の限定承認の方が使えるかもしれません。
◇対処法③:限定承認する
限定承認の制度は少し特殊で、遺産にマイナス分があったときに、マイナス分がプラス分を超えない範囲で引き継げるという相続の制度です。
マイナスの借金があり、プラスの財産があることはわかっているけれど、最終的にどちらが多くなるかがわからないという場合に有効です。
ただ、相続放棄は放棄したい相続人が単独で申し出ることが可能ですが、限定承認は相続人全員で申し出なければならりません。また、手続自体が結構複雑なため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
いかがでしょうか。
いずれの対処法を選ぶ際にも、手続きをスムーズに行うために一度専門家に相談することをお勧めします。たかの司法書士事務所はいつでも相談料無料ですので、是非一度ご連絡ください。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言書を作成するべき4つのメリットを解説
「自分の遺産相続で、兄弟や妻、息子に揉めてほしくない。」
「親の遺産のことで、揉めた経験がある。」
などといった理由で、自分の遺産相続について考えていらっしゃる方もいるかと思います。
そのような方に今回は、遺言によってもたらされる4つのメリットについてご紹介いたします。
1.遺産分割協議が難しい事が予想される場合には是非お勧めします
相続人の中に、行方が分からない者がいたり、長年連絡を取っていない前妻の子がいたり、子供がいないために妻と自分の兄弟姉妹が相続人になるものの不仲である、といったように遺産分割協議がスムーズにはいかない事が予想される場合があります。その場合、遺言書があれば問題なく相続手続きが可能になります。公正証書遺言であればよりスムーズにできます。本サイトの「遺言のすすめ」に、遺言書を遺しておくべき場合についてもう少し詳しく説明していますので、ご参照下さい。
2.相続手続きで第一に優先されるのは遺言です
遺産相続には3つの方法があります。1つ目は遺言、2つ目は相続人による話し合い(遺産分割協議)、3つ目は法定相続分による分配です。法律上、第一に遺言があればそれに従い、遺言が無ければ相続人による話し合いで決めるものとされています。相続人による話し合いがどうにもつかない場合に、はじめて法定相続分がでてきます。上記の様に遺産分割協議が難しいといった事情は無くても、相続人が何人かいれば話し合いに時間がかかったり多少は揉めたりもあるかもしれません。遺言書があればその内容通りに手続きを進めれば良いためスムーズにいくことも多いと思います。
3.相続人それぞれの状況などに応じて分配ができる
遺言書を残す際には様々な状況が考えられます。例えば、御子息3人に財産を引き継いでもらう場合でも、法定相続分の通り平等ではなく、生活に苦しそうな御子息には少し多めに、収入が安定している御子息には少し少なめにしたい、長男には家を建てる時に結構援助したので、他の二人は少し多めにしたいなど、遺言を残す方の意思を反映できるのです。そのため、相続人たちの現在の状況などを考え、遺産を分配する必要があれば、遺言書を残すべきです。
4.手間や負担を軽減できる
遺言書を残している場合だと、残されていない場合と比べて、相続の際に必要な手続きの負担を軽減できます。自筆証書遺言ではなく公正証書遺言であればかなり軽減できます。遺った妻も高齢になってるであろうから、できるだけ手続きの負担がかからない様にしたいとのお気持ちがある場合には、遺言書を残すことをおすすめします。
ここまで遺言書によってもたらされる4つのメリットについてご紹介いたしました。
遺言書を遺すことによって、家族の負担を軽減できたり、揉め事を起きにくくできたりします。そこで一度、遺言を遺すという選択を検討してみてはいかがでしょうか。

たかの司法書士事務所は海老名市を起点に、綾瀬市・座間市・大和市・厚木市・相模原市など神奈川県央地域で、相続・遺言に関するご相談を承ってきました。
「何から始めればよいか分からない」といったお悩みに、気軽に寄り添える存在でありたいと考え、ご相談は無料。
夜間や土日も柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。